うたまるです。
ここ数ヶ月ひたすら山本哲士の『ミシェル・フーコーの思考体系』を読んでいる。そしてフーコーの卓越した視点からさらなるラカンの理解が可能となった。その理解は、ヘーゲル弁証法に依拠したギーゲリッヒのユング理論をデプラスマンし、ラカンの新地平を開拓するものと思う。
もっとも山本哲士はとっくにその次元で思考しているのだが、この記事では、その領域を僕が体得した範囲内で読者に共有したい。
その道すがら、ヘーゲル弁証法とフーコーのデプラスマン(転移)との違いを紐解き、現代ユング派を次のステージにまで引き上げることをこの記事で約束しよう。
またこの記事を読めばいかに大学人がフーコーをまるで理解していないかもはっきりするだろう。
※今回の記事はいつもの記事よりグッと難解・専門的ですが、フーコーをこれから理解したいという人にとって決定的に重要です
ところで賞金欲しさに保守でもないのに、某右の懸賞論文に応募するも落ちたので、それを記事にしたが保守的内容がGoogleの検閲的なのにひっかかりこのブログ自体が危うくなる可能性を考慮し投稿を断念。
また、チケット系のサイトから相互リンクの提案がきたので執筆中の九龍ジェネリックの記事を保留し『推しの子』をベースとしたアイドル評論記事を書くことにした関係で、記事の投稿が長らく停滞してしまった。
というわけで、一刻も早く投稿するため執筆コストの低い(一日で書ける)この記事を書くことにした。
初期ラカンへの否定神学システム批判の限界
さて、日本のラカン理解ではデリディアンの東浩紀によるラカン批判が受容される傾向にある。それゆえ、初期ラカン(50年代)は否定神学システムにあり限界があるという意見が目立つ。
この意見はある程度正しい。しかし、この見方がプラチック分析を持たないデリディアンの限界を如実に物語る。これではラカンが何をしているかが全く隠されてしまうからだ。
ハイデガー存在論=ラカンという読みをベースとする東の初期ラカン=否定神学批判の要諦は、近代主体における主体の意味の単一の欠如を象徴界の究極の根拠(≒物自体)とし、その欠如を絶対化する考えのもつ問題点の指摘にあるだろう。つまり初期ラカンに見られる近代的な欲望中心主義を厳しく糾弾するものと考えられる。
他の記事で何回も否定神学システムの解説はしているので詳しくは割愛するが、それは線形的時間(自己同一性、アイデンティティ)における時間の始点が、時間系の外部にいる神への信仰を排除したことで始点=原因の無限後退(自己回帰)を生じて、時間の始点(究極根拠)が欠如化(不可能化)する意味連関系を示す。この構造のなかで欠如した究極原因=始点を求めるのが近代言語化された主語文法的な近代主体の欲望運命であり、それゆえに欲望は常に後期ハイデガー的な形而上学を生じる力動をもつ、という感じ。
ようするに神経症=近代欲望主体とパラノイア=単一の欠如を埋める妄想者の出現とは同時代的(同一の言説編制、近代国家編制的)な現象だということ。
※僕は東浩紀の否定神学論は読んだことがないので、これはあくまで僕の思う否定神学システム批判の圧縮した概要に過ぎない
確かにこれはある程度は正しい。
ただし、これは初期ラカンの理論内容においてしか成立しない。つまりハイデガー存在論と初期ラカンとでは理論プラチックが根本的に異なる。ラカン派にしてここを見逃してしまうのがラカン派の限界であり、この限界はラカン派のフーコー/山本への無知に起因する。
さて、フーコーの思考技術、その白眉の一つは客観化の客観化にある。
客観化の客観化とは、たとえばリンゴとか、あるいは何とか理論の具体的な理論内容といった対象について、それを対象化・客観化する行為自身を対象化・客観化する思考技術をなす。
このようにいうとそれはカントの超越論的哲学にもいえることで、フッサールを完成者とする相関主義哲学の基本だろうと思われるかもしれない。そこでフーコーの真理相関主義的なプラチック分析と近代哲学の欲望相関との違いを以下に示す。
現象学的相関主義のなす客観化の客観化=述語‘’性‘’理論とフーコー/山本のなす客観化の客観化=述語‘’制‘’理論(場所理論)とは明白に違う。
現象学は主体や実存を言祝ぎ、ある種の内面を哲学的思考領域の聖域となすもので、いわばデカルト以来続く欲望編制において、欲望の可能条件を開削して欲望を弁証法として動的に持続可能化する自己技術。
対するフーコーのプラチック分析の自己技術は、内面だとか実存の地平に対するメタ地平から、客観化する客観化のそのまなざしを、現象学的内在ではなく、外在性として、制度や建築空間、言説編制において分析し欲望をデプラスマン(転移)する自己技術。
このフーコーの思考技術において初期ラカンの否定神学システム=欲望論を洞察すると、ハイデガー存在論とラカンがまったく別だという事実が浮き彫りとなる。
詳しくは、ラカンの無意識について解説した当ブログ記事を読んで欲しいがラカンの象徴界とは言語空間ではない。言語場所(理論場所)である。
つまりラカンの主体の疎外(S1→S2)の理論や象徴界なる思考ツールは、主体と言語空間との関係をあつかったものではありえない。
もし仮に、そのような言い方をラカンがしていたとてそれはない。
そうではなくラカンの理論体系は、大他者がそれ自体で価値付け=欲望を構造的に内在しているという事実を暴く。
対するハイデガーでは現存在/世界内存在といって主客二元論を回避するが、そのじつ、実存還元をなして内在化してゆく近代欲望編制をなす。
それゆえ山本哲士が鋭く指摘するように、世界内存在=社会内存在をなす。これは空間編制を蒙るもので、移動主体/空間という主客分離の二元論的編制を自明化(近代欲望主体の自明化)したうえで、そのアプリオリを提出する水準にとどまる。
こ点でハイデガーは、およそ西田幾多郎の場所論とは無縁といってよい。
つまりドイツ語のザインが~であると~があるとを区別しないゆえ、ハイデガー存在論では場所水準が排除されてしまい社会内存在となる。
対するラカンは現象学的内在性(欲望編制)から欲望を対象化・客観化などしていない。
象徴界という言語領域・理論領域がそれ自身として構造的な価値付け=欲望を生じるという場所水準から欲望を記述しているのだ。
であるからラカンの象徴界や大他者とは言語空間ではありえず言語場所に他ならない。
※場所とは主体と空間との非分離にありアニミズムに近い存在体制をなす。場所とは場所自身が述語行為する水準で日本語はそもそも場所語でありそれゆえ主語=移動主体がないとされる
まとめよう。
東のラカン=ハイデガーという否定神学批判は両者の理論内容の問題点を提出しえているが、両者の理論プラチックの相違を完全に排除している。そのため両者の理論プラチックに対する読みが完全に排除されている。これは思考内容がもつ思考内容の外部を排除することに等しい。これがデリダがプラチックを排除してしまっていることの最大の問題となる。デリダは差延においてもそうだが今=行為の水準を消し去る悪癖がある。ここにポストモダンの限界があるといってよいだろう。
フーコーはこのように排除されてしまう言説プラチックをディスクールの現実性が排除されるといってプラチック分析を徹底する。
さて、以上から我々はここに哲学史をこのように言わねばならない。
フッサール現象学は欲望相関主義という哲学的達成において、つまりエポケー(存在論的な転回として主客の因果関係の反転、視点変更)によって主客二元論というアポステリオリの認識のアプリオリを暴露し、二元論モデルを解体、そのことで述語性の自己技術を達成する。まさに哲学史に残るコペルニクス的転回といえよう。
さらにフーコーが第二のコペルニクス的転回をなす。それが近代欲望編制の正嫡性を懐疑し欲望編制を限界づけること。そのことで個人が心を病むのではなく言語場所=ディスクールが心を病むのだ、という外在性の地平を切り開く欲望編制のデプラスマン(転移)をなす。これぞ哲学史におけるセカンドインパクトといってよいだろう。
ここで欲望を転移するからといって、欲望が消え去るというのは間違い。そうではなく欲望は中心化されなくなる。だから現象学とフーコーは競合関係にはない。
周知の通りと思うが、この欲望の転移をフーコーは古代ギリシャにヒントをえて快楽プラチックに見出し欲望から快楽へといったのである。もちろんこれは後期ラカンの欲望(象徴界)から享楽・欲動(現実界)への移行と完全にリンクする。
もう読者にはお分かりだろう。
以上からハイデガー存在論と初期ラカンではまったく理論プラチックが異なる。理論内容の水準から見れば確かに両者は否定神学システムだろう。しかし客観化の客観化(プラチック分析)から両者の理論の構築すること、という行為を、つまり記述された理論内容からは常に排除されてしまう思考されたものの行為を洞察してみれば、初期ラカンとハイデガーとの差異は誰の目にも明らかなのだ。
ここにデリディアンの限界がある。それゆえデリダはポストモダンから一歩も出ていない。国家編制の内側から国家編制に依存して国家編制を否定する不毛、それゆえのプラチック分析の欠如、それがデリダの限界であろう。
もっとも僕はデリダについてはまったく詳しくないので断言はできないが。
フーコー的にいえば、ラカンとハイデガーでは知がまったく違う。
またデリディアンのテキストの読み方はディシプリン的、規範化社会的な水準にあり、アプリオリのアプリオリを排除していることも以上から分かる。
といって、他の論考の甘さを叩くだけではそれこそフーコー的な読みから外れるのであるが。
すっかり書き忘れたが、現象学では内在的な条件のアプリオリ、フーコーでは外在性から歴史や制度条件のアプリオリ=アルシーブが問われる。アルシーブとは言表の出現を規定する言表の歴史的収蔵体みたいなもの。言表とは言説の最小単位でようするに叙述=言説を構成する単語みたいなもんでそれ自体で実定性をもつ。
この言表の実定制が機能と呼ばれ、それが対象編制、言表行為編制、概念編制、戦略選択をなすのだがこのあたりの細かい解説はブログ向きではないので気になる人は山本の専門書を読んで欲しい。
現代ユングとヘーゲル弁証法の限界
フーコーといえばヘーゲルとの対立が印象的だろう。ことあるごとにヘーゲル的な歴史観や考えのアンチを記述している印象が強い。
またヘーゲルといえば現代ユング派のギーゲリッヒのユング理論の中核を担うもので現代ユング派の理論的支柱をなす。ユングが提出する個性化の過程(自己実現)を現代ユング派はヘーゲル弁証法、とりわけ行動する良心(アニマ)と批評する良心(アニムス)との自己関係に見出している。
さて、ヘーゲルもまた近代主体的な歴史の同一性をなし、人間欲望=自由意志を賛美する傾向にある。
そこで弁証法によって、主客二元論を解体する(そのアプリオリを提出する)水準をなす。
またヘーゲルは全体性や体系、フレーム、まとまりとしての規範を完成させることを価値付ける。この価値付けは欲望が欠如を埋め立てる自滅的ベクトルをもつことと完全一致する。
しかし、そのうえでヘーゲルはこの欲望の自滅を克服するために弁証法をなす。その要諦は、動的一致である。いわば存在論的差異=欲望を欠如=矛盾としてつど開くことで動的にそれを一致(自己実現)するという水準をなす。もちろんこれは現象学の理念と変らない。
しかるに極めて欲望肯定的哲学といってよい。
フーコーの場合も動的一致を結果的になすのだが、その価値付けの重心が異なる。
それゆえフーコーでは全体や体系、フレームといったまとまりを嫌って、体系ではなく叙述化することの体制としてディスクールを規定し、いわば全体に先立って全体を構成する諸行為の側に着目するとともに、さらにそこから行為が蒙る全体、体系の側からの存在規制・行為規制を外すという思考操作をなす。この思考操作をフーコーは出来事化することと呼び、絶対的に重視する。
フーコーのデプラスマンとヘーゲルの弁証法の何が違うか、ここが問題となるわけだが、以上からもその違いがある程度分かるだろう。
フッサール/ヘーゲルもフーコー/ラカンもともに述語への重心移動は変らないのであった。
であるから両者とも行為水準を観てゆくことや客観化の客観化は成されている。それは既に見てきた通りだ。
ここで両者の違いをはっきりさせるためヘーゲル弁証法における行為の機能・役割を確認しよう。
ヘーゲルにおいて行為・述語は行動する良心と呼ばれる。これはそのつど行為者が、直観的にそれを正しいと信じて身体的・具体的に行為する水準をなす。
さらにヘーゲルでは批評する良心が重要な役割を成す。批評する良心とは自らの直観的な行為・行動(行動する良心)を振り返る近代的なリフレクション=内省の作用であり、いわば行為の行為自身による否定機能となる。
ようするに近代的な行動する私とそれを私として内省・対象化する私との自己差異の弁証法的自己関係を示している。
わかりやすく喩えれば、映画監督やその監督の映画作品(イメージ)が行動する良心、その映画の具体的なイメージ内容を分析してイメージの具象性・ドクサを解体し普遍性(普遍的意味)を取り出すのが映画批評家であり、その批評家の批評文が批評する良心といった具合だ。
つまりヘーゲルでは行動・行為の直接性はイメージや行動規範といった枠・全体性・具象性といったものの行為規制/存在規制を蒙り、硬直化すると考えられている。
※存在規制とはカントでいう純粋統覚のことで、ノエマの同一性によるつどの存在・現象学的志向性が制限されてしまうこと
すると規範化することの規範化や西田の作用の作用の排除といったことがおきる。これが全体主義的な権力関係における知のあり方ともなるが、この行為が自身との絶対的一致を欲望しだす欲望行為の自滅的規制を外すため、ヘーゲルにおいては批評する良心が重視される。
この批評は行為に対する純粋なネガであり実体がなく、行為自身に付随する否の機能と見なされる。
※これはギーゲリッヒ的なヘーゲル理解によるもので哲学者のヘーゲル理解とは異なるかもしれないが、このブログでは常にギーゲリッヒのヘーゲル理解をヘーゲルのベースとする
さて、もうお分かりかもしれないが、目的的な行為のプラチックを解放するものはヘーゲル/ユングではネガ/内省機能に過ぎない。
これは欲望が自身を欠如とみなすネガに対応するだろう。
ラカン派の視点から説明すればこの意味が分かる。
ようするに現実界がネガ化・欠如化されて、現実界の意味するもの(S1)がたんにリフレクション=欠如としか言われていない。
※意味するものとは言語的な意味における剰余や欠如のこと。ある現実の対象を言語的意味体系から把握すると、現実の対象には、その意味体系から溢れてしまう意味の外部(現実界)があり、この意味の外部が意味付けを希求するため、それを意味するものと呼ぶ。たとえばある人を悪人と意味づけるとその悪人の現実行為の内から悪という意味付けに反するものが排除されて、その意味の剰余/欠如が現実界を構成するという具合
そしてこのことが、ヘーゲルが全体性・まとまり・体系といった塊の側に視座をとってその完成に価値付けを置くことの理論的帰結なのである。
はたして、このような内省の契機を行為のネガ水準におき、
行為のポジとなる意味するものをネガ化する眼差しはユングの理念に適うものであろうか。
とうてい僕にはそう思えない。
ヒルマンにて多神教に傾倒しすぎたそれをバランスして近代欲望を価値化するなかで、ユングにあった大切な場所の水準が排除されてはないだろうか。
欲望を否定しろといっているのではない。ここは多くの現代思想がミスリードしてしまっているが、フーコーのデプラスマンは決して欲望の敵対者ではない。
だから弁証法が否定されることでもない。そうではなく中心を欲望から外すこと、つまり欲望それ自身を限界づけ、そのことで翻って欲望をよりよく生きることを実現するもの、デプラスマンである。
ここから現代ユング派の田中康裕のイメージの直接性批判にもさらなる批判をなさねばならない。
田中康裕はユング派にあってラカンが重視する誤認の問題を浮き彫りにした人物で現代ユング派を語るうえで欠かせない。
田中はギーゲリッヒの批評する良心(アニムス)論に頼って、ユングのイメージの直接性の考えに警鐘をならす。
つまりイメージ/行動する良心にそのまま直接没頭すれば古代的な状態として、かえって抑圧が進み弁証法的自己関係が妨げられるという具合だ。
しかし、ここで意味するものの水準を取り出すと話が変る。ユングのイメージの直接性をイメージの核としての意味するもののことだと見抜くのである。じじつユングはイメージには言語的に意味に回収不能な行為的意味性があり、それがイメージの直接性だというニュアンスのことを言っていたはず。
したがって言語の意味の核をなす意味するものをイメージ/想像界の水準に転移してイメージの核として、つまりイメージをイメージとして具象化してゆく行為を具象性の外部にあるイメージするものとして読むのである。
このように内省することの行為をネガからポジへと、つまり現実界へとデプラスマンしてみれば、ユングのイメージの直接性にあらたな水準、ユング版の現実界を見出すことができる。
この外部を読みこむ場所制の理論へとユングをユング自身の記述において転移すること。
ここにさらなるユング心理学の個性化の過程があるだろう。
念のためヘーゲルとフーコーの違いの要点を改めて以下に纏める。
フレーム・全体性・体系といったまとまりの側に価値付けをもつ近代欲望では、不可避に全体規範からの差異・欠如といったものが罪や過ちとして排除される力学を生じる。
これがフーコーによるキリスト教の告白の自己技術批評に通じるが、
つまりヘーゲル弁証法においてすら、理不尽や禁欲を引き受けろ、という主題が中心化するきらいがある。
すなわち、ヘーゲル弁証法では全体規範からのつどの差異・欠如を全体性のための贄として全体規範が吸収してゆく感じになるが、そこでの価値序列は全体規範の側に優位性があり、それゆえ無謬などないのだ!と罪と欠如の引き受けを主題化しうるということ。
この主題が無謬を彼岸に幻想するのはラカンを引用するまでもなく道理である。
そこで、この意味するもの(行為水準)をネガ化してしまう欲望の弁証法の限界を超えるため、弁証法を限界付ける(欲望や弁証法のプラチックを見抜く)のがフーコーである。
そのためフーコーは欲望をキリスト教の告白の自己技術に見出し、パストラール(司牧)に対する告白・告解における肉欲の完全なる言語化=原罪化と肉欲の自己化・身体化という欲望のタームを批評する。
ラカンの欲望論が欠如論であればフーコーの欲望論は原罪論といえよう。
ここを超えるために欲望編制の歴史条件を古代ギリシャに遡って系譜学的に探り、諸プラチックを出来事化して、欲望編制を転移する条件を探ったのがフーコーであり自由プラチックである。
そしてフーコーのプラチック分析などの思考技術そのものが欲望編制を超えた自由プラチックの技術だということが肝要となる。
また欲望や弁証法の欠如/罪論は規律化権力や規範化社会論など多くのフーコーの論考に密接に関わる。
たとえばディシプリン的な学校のクイズテストがわかりやすい。学校ではクイズ方式のテストにより個人をスコアリングして個別化、序列化、規格化する。このテストが模範解答・全体規範からの逸脱を罪、欠如、間違い、過ちとして減点化し身体にすり込み続ける。これによって間違い・差異を排除して規範へと自発的・主体的に従属化してゆく欲望主体をつくりだす。
※学校のテストでは間違いは減点=ネガであり数値の欠如としてしか意味化されない
これが今日のネット言説に致命的な仕方で浸食し、ネットでは敵の言動をリストアップして模範解答を言動と突き合わせ、真偽判断にかける。もし模範解答からズレた言動があればそれを根拠に間違いを断罪してフルボッコ。これを正義執行と勘違いして狂喜乱舞するのが日常化している。
まるでテストの採点者さながらであり、誰もがクイズ試験の採点者(大他者)の立場から他者を糾弾する。
こうした今日の問題を考えるうえでフーコーの理論は極めて有効であるわけだ。
またしばしば、保守派に見られる理不尽は必要だ!とやたらと理不尽の必要を強調し、理不尽(罪)の引き受けを主題化するタイプの言説は、普遍規範主義者にこそみられるが
この理不尽主題の言説も独断論的規範主義または、弁証法的規範主義の効果のどちらかであると分かる。
※弁証法的規範主義者がここまで理不尽を立てるのはやや考えにくいが弁証法言説の実際作用としてこうした言説が生産されうる
このような言説がそれ自身で理不尽の完全排除を欲望させるプラチックをなすことはいうまでもないだろう。保守派は哲学理論が弱過ぎる。
かかる言説を限界付けること、それが意味するもの・プラチックを分析するフーコーの思考技術となる。
繰り返すがフーコーは理不尽や罪を不要だとは言っていない。そうではなくそれらを主題化・中心化しないこと。そのためにそこから価値付けを転移して、差異や欠如の側を価値付けするのである。
つまり普遍規範の設立にあたり理不尽や罪の必要を中心に語る言説を絶対化する限り、
普遍規範・フレームの側の価値付けを中心化する限り、
理不尽や罪を完全に消し去ることが欲望・幻想され続けるだろうということ。
そこで、その欲望や弁証法水準を消し去るのでなく、その欲望のもつ価値付けを差異や誤謬の側へと転移して脱中心化するのがフーコーの戦術となる。
このためにフーコーは意味するものの水準にあるプラチックを徹底的に重視する。ヘーゲルでは意味するものをネガ化してしまうために限界があるというわけだ。
内省をネガとしてしか確定できないヘーゲルでは内省はあまりに辛いのである。
内省は意味するものの存在の輝き(積極的行為)である!という水準をフーコーは切り開いた。このことで僕たちはよりよく自由に自らを振り返ることができるのだ。
何回も繰り返すが、両者は敵対しない、フーコーは罪を消し去ったりしない。
といっても、まだフーコー/ラカンの哲学的・心理学的達成の意義が読者には伝わっていないかもなので、実際にフーコーの思考技術を駆使して、読書のプラチック分析を簡単に提出してなんとなくその感じをつかんで欲しい。
百聞は一見にしかず、まずは実際に読者のその目で、上澄みだけでも確認してもらいたい。
読書のプラチック分析
昨今は出版不況から本のステマが横行し、本そのものが本商品の大量消費を促す広告と化すに至る。
そんな時勢にあって、本の読み方、ハウツー本まで生じている。このような広告の暴力において、本の読み方を示す知はどのような構成となるのか、これをフーコーの種別的プラチック分析の思考を頼りに読書の仕方のプラチック分析として明らかにしたい。
これで既存の哲学では隠されて見えないプラチックがフーコーの思考技術から明らかとなるだろう。
昨今の流布する読書メソッドは、僕の知る限りそのほとんどがデカルトの方法序説っぽい。
つまり、
①最初に明瞭に、意識、言語化、一般化できる方法を考える。
②次に本の種類や本を読む目的を細分化/規範化/パターン化し、読み方を類型化し箇条書き。
③さらに類型ごとに読破理解という目的の達成にかなうプロセスの因果関係を分析して方法を順序化してこれも箇条書き。
④最後に読書の全体の営みから確立したメソッドを点検。
多少の差異はあれど概ね、これに近い思考のフォーマットで読書メソッドが提出されていると思う。
あるいはこれは、読書感想文の書き方とか言語化の仕方と置き換えてもかまわない。読書感想文であれ、何かの言語化や映画批評の書き方であれ、それは本や映画をいかに読むかの提示に限りなく近いからだ。
このようなハウツー的な知の編制を問題構成したのはフーコーである。
ここでは、このややデカルトっぽい主客分離の知の編制に、主体化=従属化を読み、かかる知の編制に潜在する全体主義的な権力関係を見抜く。
ではさっそく分析しよう。
話は簡単で、イマドキの読書メソッドはプラクシス思考による目的のすり替えが生じている。
つまり正しい最適な本の読み方を問うとき、客観的な方法論の確定が暗黙に目的化してしまう。
このような価値付けが方法序説っぽい知に内在しているといってもよい。
※このような理論自身がもつ主体を超えた価値付け(実際行為)を言説プラチック・理論プラチックと呼ぶ
言うまでもなく、読書家が本来、本の読み方を問う理由は自分にとっての最適な本の読み方の確定であり、自分の固有性を消去して成り立つ客観的な方法などではありえない。
ところが上記の思考に頼ると行為水準・プラチックが排除・規範化され続け、一般化が繰り返されてしまう。
このことで実存的な読書メソッドが類型化と一般化を反復し、求めるメソッドが客観的読書メソッドであるという欲望の誤認作用が生じる。これによって実存的目的と客観的目的との存在論的差異の顚倒・誤認が起きる。
※プラチックとは実際行為のことで目的的なプラクシスと異なる。つまり行為者の意図をこえた行為の実際作用を読むのがプラチック分析となる
まとめよう。
ようするに、本を読む目的や本の類型化・規範化は一般化・客観化をなし、これにより、本と私との関係の類型化=自己の一般化=規範化することの規範化が生じる。
つまり貴方は何のために本を読むのか?と読書メソッドなるものは我々に迫るのである。そして、貴方の目的は①云々、②云々、、、のどれですか?となり、我々は、その規範・目的へと自己の読書行為(欲望)を目的的に去勢してゆくのである。
これを僕は知のディシプリン化の論考を参考に、規範化することの規範化と呼ぶ。
したがって読書メソッドにおける本や目的の類型化は私の規範化=自発的従属化なのである。
これが欲望における存在論的差異の誤認を介して生じるのだということ。それゆえ人は自由意志によって自らを規範へと従属化する。
本来とわれるのは私と本との一般的関係ではありえず、私と本との一般的意味・目的を超えた絶対的関係なのだ。
また、他にも問題がある。読むとは本来、欲望を欲望することであり、それ自体が目的をなす。
にも関わらず読書メソッドでは読みを目的から手段へとずらしてプラクシス化/手段化する。これは行為と目的を分離して読む行為を目的規範によって去勢する効果をなす。
もちろん誰だって~を知りたいから読む、というようにきっかけは読書の外部にあるだろう。
しかし、いざ読むというだんで読んでいるただなかで、そのような外部目的の意識は消失するとまではいえぬとも、限りなく減衰するものである。
つまり、この著者は何を言わんとしているんだ?(近代的or弁証法的)とかこのテキストは何を意味している(プラチックしてる)のか?(フーコー的)という読みがまず何よりも読みを継続せしめ深める動機をなす。
これが読書なるもののプロセスとなるが、このプラチックが消去されて最初の外的な目的・きっかけが絶対化されてしまい、読書の読みがまるで深まらなくなる。つまり読む述語行為が主語目的の規制を受けて全体主義化するということ。
始発の本の外部の動機・目的を絶対化すれば、コンテキストなど排除され、イマドキの大学院生によくある自己中読みが大量発生するのは避けられない。
※よく本を読んだ数を自慢する人に対して、読むことが目的になっているが読むのは手段で本末転倒というダメだしがあるがこれは厳密には間違いで、読んだ数という読みの外部を目的とし読むことを読書主体が数として所有する権力所有論的な編制にあることが最大の問題となる。また意味するものは意味化を停止せず意味してゆかねばならない
現代は、こうして人文学が死んでゆくフェーズに来ているだろう。
このように読むという行為であり営みの側が優位であり、この行為を目的・主語から解放することがプラチック分析なのである。
だから、このように読書メソッド論を問題構成すること、それは読書メソッド論における読書の問題点=要点の抽出という問題構成・客観化を問題構成・客観化する思考技術であり、これこそがフーコーのプラチック分析なのだ。
このように問題構成をなして差異を構成することで読書行為そのものが主語目的の規制から外されて解放されるわけで、これをフーコーは自由プラチックと呼ぶ。
そのうえで著者の欲望を欲望するという近代的な読みがパノプティコン的な欲望の従属化を生じる力学を内在するというところまで分析しているのがフーコーといえるだろう。
ともあれ、このように身近な思考フレームに内在する思考プラチックを洞察して行為を解放し、さらに思考フレームをフレームではなくプラチックの束へと還元して、それをフレームや体系というヘーゲル的なまとまりとは峻別して【叙述化する体制】だと視点変更してゆく、このことで叙述かする体制を転移する条件を探る、ここがフーコーの哲学の決定的な核心である。
重要なまとめ:現在的思想課題におけるフーコーの要約
フッサール/ヘーゲルとフーコーとの異同をここでは圧縮した要約として、今日の思想的関心に即して提示しよう。
まず今日の思想的課題は人間欲望/自由意志は可能か?という問いにつきる。
この問いを巡り諸派で対立が起きている。
これを不可能とし人間欲望の際限のなさを忌避して、神による禁欲の世界への回帰を目指すのが古典主義を標榜する伊藤貫らの勢力。
次に際限なき欲望と自由を至上の幸福とするのがテクノリバタリアンやネオリベ、シカゴ学派系の人たちだろう。
これら二つの闘争は、思想史における独断論VS相対主義の変奏の一形態と見なせる。
しかるにこの二つの思想の限界は哲学的に明白。
そこで、この不毛な対立を超えるため、禁欲VS無限の自由という二項対立が自由のドクサ(憶見)からくると見抜き、自由の経験的な認識のアプリオリを暴くのがヘーゲルである。
事実、現象学において人間自由なるものの本質は不完全=差異や禁欲(断念)・葛藤の類いにあると分かる。
※もし自己の自由な意志決定=選択において葛藤がなければそれは私の意志決定とは自認されえず、たんに選択の余地はなかったと認識されておしまいということ
したがってある種の禁欲・葛藤・欠如が欲望主体の根拠となっている。そこを洞察して、フッサール/ヘーゲルは人間欲望をサステナブルにする弁証法の水準を開く。
つまり弁証法においては
禁欲VS自由・欲望ではなく禁欲即自由・欲望へと欲望自由が転換されるのだ。
この欲望の弁証法によって独断論と相対主義の不毛な二項対立を乗り越えるのが現象学の達成の一つである。
これに対して、フーコー/ラカンも同じく禁欲的なもの・罪が欲望を創り出すことを見抜く。
そのうえで、さらに欲望の誤認(罪なき欲望主体があるという誤認)のメカニズムを暴き、弁証法と欲望が構造的にもつ全体性・体系・フレームといったまとまりへの絶対的な価値付けを外して(弱めて)意味するもの・全体系から逸脱した行為を重視し、禁欲や罪なしに欲望を限界づけること(内省を実現すること)を実現する欲望編制のデプラスマンを達成するのがフーコーの思考技術といえる。
いわばフーコーは弁証法の絶対性を限界づけたのだといってよい。弁証法を駆逐するとか欲望を消し去るのではない。あくまでそれらを脱中心化して限界づけるのである。
このフーコーの戦術的なディスクールがいかに今日の政治・経済の世界的非常事態にたいして重要であるかは明白であろう。
ところでフーコーにも弱点があり、フーコーのセクシャリテ/セックス論はジェンダーアイデンティティというフレーム・まとまりを一切語らない。
このことで一部のフェミニストからのウケがわるい。つまりフーコーでは主体の問題が消去されていて、女性のアクティブな政治主体を論じられないのである。
その点、竹田青嗣らの現象学は述語を立てつつ主体というか実存を徹底的に可能とする特徴がある。その点で両者の比較は非常に興味深いのだ。
終わりに
僕なりに山本哲士の切り開くフーコーの思考体系の中核的なところを、かなり分かりやすく提出したつもりである。ただ一日で書いて見直しして投稿したので、チェックがあまくなったかもしれない。
まだ本を読んでいる途中で僕のフーコー理解には多々、甘いところもあるが、その核心的部分はなんとか捕まえた、という手応えを感じている。至らない記述が多いとは思うが、なんとかある程度の人には哲学や深層心理学の重要性が伝わる記事になった、ということにしたい。
かなり苦労したが、どうやら半年くらいかけて山本哲士の本と向き合えば、フーコーに関しては最低限のところは掴めるようである。
もっともラカンぬきではこうはいかなかったと思う。ラカンの理解がフーコーを最低限領有してゆく上で大変な助けとなった。
この記事でフーコーでしかなせない次元もある程度はっきり示せたのではなかろうか。
僕としてはヘーゲル弁証法とフーコーで何が違うのか、ここを特定するのにアホみたく手こずった。これは本当に苦労して考え続けてようやく、最低限の理路明瞭な答えにたどりついた。
今度こそ僕のなかでこの問題は解決したのだと、そう願いたい。
何ヶ月も考え続けてようやくである。なにせヘーゲルも行動する良心といって行為水準を中心にしているので、じゃあ何が違うんだとなり、全体に視座(価値付け)をとるヘーゲルのパースペクティブと諸プラチックに視座をとるフーコーのパースペクティブとでの主客二元論の超え方の違いが何を意味するのか、実際の弁証法的な自己関係や真理生産において、いったいどのように異なって、どういう問題が生じるのか、ここの特定が本当に苦労した。
イマドキは三分考えて分からないことは、もう考えない、となるのだろう。これで人文学研究だと騒ぐイマドキのネットで荒稼ぎする院生には本当に呆れる。そんなんで知の探求ができるわけないだろう。
死ぬまで分からないことだけを考えるのが、知の探求、この精神なくして研究などとは荒唐無稽。文系大学教育は本当に終っているとしか言い様がないと感じる。
さて、山本哲士の新刊が出ている。ベースショップで購入することを勧める。
山本の本の威力はこの僕の記事にも少しは表われていると願いたい。僕はもう半年だったか、それ以上か、山本の本以外ほとんどまったく読んでいない。というかずっと同じ本、ミシェルフーコーの思考体系しか読んでない。
まだ読み終わらないのだ。メモ帳は三冊目に突入している。
近代哲学の入門なら竹田青嗣、それ以外の哲学は山本がベストだと思う。
僕の理論生産がその威力の実証になると願いたい。
とくにフーコーを山本以外の本で学ぶのはあまりに無謀と思う。山本の哲学は恐ろしく驚異的で、圧倒的な水準にあると思う。
またゲーム好きなら小島監督作品は外せない。小島作品はそれ自体で哲学になっている。ゲームをデプラスマンしているのだ。
ちなみに本の読み方は本が決めることで、本に任せることを僕は推奨する。なんだか頭に入らないなとなったら本が、お前は読むのが速すぎるから遅くしろ、と訴えているのである。
だからごちゃごちゃと本の読み方などと考える必要は無い。最初から本がその答えをつど提示してくれている。

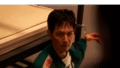
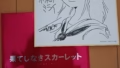
コメント