※四月に記事を投稿してないことに気づき、考えがまとまってない状態で焦って書いたため、四象限理論の説明以降が冗長で雑な仕上がりに。また記事が長くなりすぎたため見直しが行き届かず荒削りな内容に
うたまるです。
今回は西部邁の最後の著作『保守思想の真髄』で書かれていた西部保守哲学の中核的理論となる言語の四象限理論を軸に、フーコー、カントから西部哲学を示し、その思想の本質を明らかとしたい。
ここでそれを明らかにする手法、つまりこの記事の思考の技術はそれ自体で、西部思想の実践となると思う。そのような論理構成をなすのが当記事の思惑。
またこの記事は西部邁の保守哲学のやや専門的な解説・批評となるので、想定読者レベルを表現者塾の塾生に。つまりいつもの記事より数倍小難しい。
といってもある程度、思想哲学、深層心理学に興味ある人にとってなら、とくに現代の哲学系言論人の全体的な見晴らしをつけたい人には興味ある内容と思う。
※僕は表現者塾の塾生を知らないのでどのレベルにあるか分からないが、塾にまとまった金を払って学問し、西部を領有して保守哲学を担おうという志ある人の集まりと想定、ならこの記事くらいは読めないといけない
さて、いま言論界に足りないのは簡潔な見晴らし、現代日本人の哲学者の鳥瞰図だと思う。この全体の把握がないと、たとえば現象学派で近代哲学派の竹田青嗣&西研&苫野&橋爪、ポストモダン系の國分功一郎(スピノザ)&千葉(ドゥルーズ)&松本卓也(ラカン)、西部門下の浜崎洋介(福田恆存)&藤井聡グループ、その他古典主義系やポストモダン肯定派の保守の見解の異同やその理由もつかめない。すると自らの思想の現在地さえ分からない。
※同じ保守でさえ、みんな思想の根っこが根本的に違うのにヨウブン系保守はカモなので何も知を与えられていない
そこで、この記事では、西部入門に留まらず、各思想に所属する初学者やこれから思想的基盤を探ろうという者、とりわけ保守系の人に、ざっくりと、これら諸派の理論的位置関係を提供したい。
※この記事では主語制を問題として扱うが主語に関して、言語理解がカッスカスの論理言語学の人による見当外れの支離滅裂なクレームがしつこかったので猿にも分かるようにここで当ブログにおける主語の意味を示す。
現代英語に典型される近代主語とは主の語であるから、述語に先行しそれを従属させる一面がある。この根拠を示そう、近代以降の僕らは自分を自由意志の主体として自己認識し、その自由意志の自己自身=主体を主語に代表させてコミュニケーションしている。だから主語が述語を持っている側面があるのは正しい。もし逆に主語が述語に従属するという意味合いしかないのなら、そもそも自由意志の主体を示す語として全く機能しないので絶対的に矛盾する。また僕はそもそも英語の主語ですら本当は述語に従属しているが誤認として述語を持つのだといっている。なおこのようにいうとSubjectのサブは従属の意味じゃないかとアホな批判がくるかもしれないが、これはフーコーのキリスト教の主体化=従属化やラカンの理論からも明らかなように矛盾しない、そもそも僕もフーコーも従属化が自由意志=近代主語の問題だと言っている
※僕は深層心理学専門で哲学は詳しくないので(ただし普通の院生や二流大学教授より遙かに上)、この記事での哲学者のマッピングはあくまでも僕個人の大雑把な解釈に過ぎない
※一部読者からかなり舐められていることが分かったのでこういう書き方をしないといけなくなった、当ブログでは理論生産もしない実力を実証できないスネ夫の反論は相手にしない
西部邁の四象限理論
最初に四象限理論から示そう。僕は記事のために読んだ都合で保守の真髄しか読んでないのだが、そこに書かれていた概略を頼りに適当な精神病理学と哲学の理論をつかって、これを解説する。
※保守の真髄ではかなり説明がオミットされ、論理の結論だけがタイトに示されていたので、僕なりに整合性のとれる解説をしてみる
四象限理論の位置づけ
さて四象限理論は西部の著作を読めば明らかだが、彼の理論と思考の中核にあって、その哲学理論においてもっとも体系的なものとなる。いわば西部保守思想の核心にして結節点をなすコアセオリーといってよいだろう。
にも関わらず、西部門下の人で四象限理論に触れる人を見たことがない。無料の動画では触れないようにしてるのだろうか。
西部の本には自身の渾身の四象限理論に批判を含めてリアクションがまったくなく残念という旨が書かれていて、僕としてはこの理論をこうして公に議論してゆくことが必要に思う。
西部は著作において、ヴェネディクト、中根千枝、和辻、イザヤ・ベンダサン(山本七平)その他もろもろ誰もが一度は読んだり聞いたことがあるようなビッグネームによる日本人論を極めて辛辣に批評、言語の構造分析なくして日本人の分析なしという意味合いの言論を張る。
※中根のタテ社会論は日本語の敬語(タテ関係語)の過剰さなど言語の見知からも興味深いのだが、その点が見逃されている、この西部の盲点の要因については後述する。ともあれ西部が自身の言語論に対して多くを賭けて発言していることがこの辛辣な批評から読み解ける
ちなみに四象限理論はユングのタイプ論にその形式が似ている。西部はタイプ論を知っていたのだろうか?
四象限の解説
西部は言語の根源的な特性を二つの軸で考える。まずY軸が言語・意味の顕在性と潜在性、X軸が同一化と差異化。正の数が顕在と同一、負の数が潜在と差異。
このXYの関数風グラフにある四つの象限に言語の諸機能を対応させる。
最初の機能の伝達は、第一象限(右上)にあり人間が言語によって自らの意を伝えようとすること、言わんとすることであり、言表行為に属する。伝達する限り自らの意は言語を解して他者へと正しく伝達されると期待されるから、伝達においては自他の意の同一が前提され、また伝達は言語という顕在的表現を目指すから顕在に属する。よって第一象限となる。
また意味の伝達にあるためこれが経済学と関連させられる。
経済では価値(意味)が金銭を介して交換されるわけだが、この価値交換が意味伝達に対応するということ。
※ラカンの言語論とかハイデガーの時間論をしってるとこの対応は分かりやすいのだが、僕も金の流れと存在・リビドー(伝達)を連動させて考えたことがある
第二象限(左上)が表現、これはその都度のアクチュアルな個別の状況に相関して話者が自らの意を具体的な言語で表現すること。いわば表現された言葉が表現。表現は表現された具体的な言葉なので顕在化しており、その都度のアクチュアリティや自己回帰性おいて、つど意との同一における差異を構成しうる。また後述する蓄積との差異もある。よって第二象限となる。
意⇒表現のプロセスがあるとすると、⇒が伝達に相当し、表現が表現に相当する。
意味されたものと言ってもよい。表現は竹田青嗣でいう現実言語にも対応する。
※意味するもの、意味されたものといえば一般にはソシュールだろうか、しかし当ブログではソシュールのモデルは使わず全てラカンのモデル。ソシュールでは意味するもの=シニフィアン、意味されたもの=シニフィエだが、ラカンでは逆転して意味するもの=シニフィアンS1(ソシュールのシニフィエに相当)、意味されたもの=シニフィアンS2。ラカンのモデルのが優れていると思う
また表現は政治学だという。
第三象限(左下)が蓄積、これは表現の歴史的蓄積の総体で、辞書的な用語の意味である。一般的意味・一般言語表象(竹田青嗣)に対応する。意味の歴史(痕跡)は潜在的であり、その蓄積はつどの表現との差異の蓄積において意味の多義性を過去の表現の痕跡として包摂・一般化してゆく。だから第三象限。
またこれは社会学に対応するという。
浜崎洋介も重視する木村現象学でいえばノエマ的自己が蓄積に対応する。
重要なのは表現と蓄積との関係。ここは言語の多義性の問題と密接に関連しており現象学的言語論とも密接に関連するのだが、西部の四象限理論の鋭さがよく出ている。
なぜ表現と蓄積が重要か解説しよう。
まず現象学的言語論においてはフッサールの弟子、ハイデガーの言語の意味の存在論的差異が極めて重要となる。
言語の意味の存在論的差異は言語の多義性の問題に直結するもので、非常に重要だから解説する。
※これが分からないと色んなことが分からなくなる、現代社会分析において、この意味を巡る差異の問題が人間の自由意志の誤認の問題と相同性をもち、人々の幻想の形式とも通底して社会の趨勢を握ってしまっている
さっそく解説しよう。
人はそのつどの状況コンテキストに応じて、自らの意を、蓄積としての一般言語表象を道具として用いて伝達する。
ここで道具とはハイデガーの術語で、たとえば火事で部屋から脱出せねばならないとき、目の前の椅子が窓をたたき割るハンマーとして対象化される。
この時、椅子は一般言語表象で、ハンマーが道具(表現の意)。
※家事に瀕して危機的気分を引き受けて脱出しようと自己を気遣うとき、脱出したいという欲望・投企によって椅子がハンマーとして対象化されるが、この対象を対象化する気遣いであり欲望を、現象学的志向性(指向性)と呼ぶ
つまり椅子という一般的意味(座るための家具という意味)の記号(一般言語表象)を使って窓をたたき割るハンマーという個別文脈的な意味を実現しているということ。
このときアクチュアルな個別的・道具的意味(ハンマー)とそのような状況コンテキストを抜き取られた一般的・客観的意味(椅子)との差異を言語における意味の存在論的差異と呼ぶ。
重要なのはこの差異が同一されているということ。差異の同一が起きていることに注意、もし差異の同一でなく差異だけなら、いかなる言語表現もしっくりこなくなり統合失調症となる。
西部の著作を読めば分かるが、彼は表現と蓄積の関係とに、この意味の存在論的差異を洞察してるはず。
※意味の存在論的差異はそのままイメージと客体との心理学的差異と相同性をもち、この差異の水準と分化の程度が吉本隆明の共同幻想の分化とも連動する、またこれがフーコーの権力関係や統治技術・自己技術とも関わる、晩年のフーコーのパレーシアを考えるときには、これが真実(現実界?)と真理(意味・出来事化)の差異・同一の次元でも捉えられると思う
※木村現象学ではこの差異のバリエーションとして、感覚与件(現実界、絶対的個物)と蓄積・表現(ノエマ)との差異を文字のゲシュタルト崩壊の要因と見なし、これを無限小の差異として捉えるが、この無限小の差異をラカンは現実界の物と象徴との差異=対象aとする、かかる差異の論考は哲学論理の上で重要となるが、卑近な例でいえば山本太郎がこの野菜ベクレてるというとき、野菜とベクレた野菜(感覚与件)との差異が対象a=ベクレに相当する
さて、ラストが第四象限(右下)の尺度。これは西部の保守思想の核心部分を捉える上で大事。ようするに西部は後述する認識が尺度を認知・構成可能とすると考えていて、ここに西部の保守思想のエッセンスが凝集している。
※表現者クライテリオンのクライテリオンは判断基準であり、尺度に対応するはず
尺度は、いわば言語・意味の時間的ベクトルに属する概念で、蓄積の歴史の意図や根拠、歴史の向かう先、伝統の意志、力、歴史の意がもつ企投性、歴史のアイデンティティのようなもの。
尺度は話者が自らの言語について、あるいは文化や伝統について内省・認識することで洞察可能となる。
この尺度の着眼も優れており、これは精神分析における〈父の名〉に相当する。また尺度はルソーの一般意志にも対応する。ルソーについては関係に個人を先行させて契約をベースにするからけしからんと表現者塾で聞かされるのかは分からないが、実際にはルソーはそんなに単純ではない。
※ここまで言語の本質に迫りながら、自他関係の視座を欠く
集団主義と個人主義
以上の四象限、伝達ー表現ー蓄積ー尺度から西部は、既存の日本人論を超克する日本人文化論を展開するのだった。
各国の文化を個人主義と集団主義の性質の組み合わせで論じてゆく。
ここで重要なのは個人主義は単なる砂粒の原子的個人ではないし、集団主義はたんなる全体主義ではないということ。
四象限理論では個人主義を単一の尺度を共有しつつ、個別の表現を目指すものとし、
対する集団主義を、蓄積と伝達を同一させるものとする。
説明しよう。
まず個人が独自に自由な意見をいうこと、この個別性はそもそも尺度が共有されていないと実現しない。たとえば自由の相互承認(一般意志のヘーゲル解釈)が典型だが、これがないと相手を黙らせる自由まで生じて個人主義が成り立たない。
近代的個人はそもそもが諸個人が一様に等しく同じ人間として対等であるという人権意識の尺度なくして成立しないということ。
したがって個人主義とは、原子的個人としての意識と、それを成立させる相互的個人(相互承認関係)としての意識の合成からなるという。
なお、尺度は伝統や歴史の意なのだから、人権意識や自由の相互承認を尺度するのはおかしいと思われるかもしれないが、伝統の意はそもそも未来への意志を内在しているからこそ僕たちの指針たりえるわけで、したがって、人権意識なども尺度に属する。どちらも、どうあるべきかという理想の水準にある。
※伝統の具象的な表現を慣習や儀式とすれば、それら具体的表現の背後にある意が尺度・伝統なのだ、だから尺度は空間でなく空間の連なりを物語り的に意味づける根拠としての時間の流れ、ベクトルに属する。また伝統・尺度を単一の不在として洞察する傾向が西部保守にはあるかも。西部語録でいう態度(尺度)は具体的な習慣や意味をもたないので具体的次元では欠如しているということ
集団主義はといえば、これは全体主義を考えると分かりやすいが、全体主義では一般的・画一的な法・言語が絶対化しており、いわば表現の現在的自由がなく、一般的意味たる蓄積に伝達と表現とが差異なく完全に一致することが強制される。
この場合、伝達はまったく遊びのないカチカチに凝り固まった蓄積・一般的意味によって強力に統制されることとなる。かかる伝達と蓄積との関係における蓄積の支配的作動による伝達の過剰な従属化が全体主義といえる。
このように集団とは蓄積と伝達との差異の一致をめぐるバランスから構成されるということ。
※蓄積が伝達や表現に与える過剰な規制を木村敏はポストフェストゥム=鬱病性格=自身へ遅れをとると呼び、近代的存在体制として扱った、ポストフェストゥムはフーコーでいう近代の従属化の問題に対応する、深層心理学やポストモダニストでは近代の主体の従属化問題は神経症心理に帰結し、現存在分析では鬱病心性に帰結する、ただしクラインの対象関係論では近代=鬱病=抑うつ体勢として示される
したがって集団主義とは、開放的集団と閉鎖的集団とに分かれる。閉鎖的とはもちろん過剰な従属化を強いる全体主義のこと。
さて、西部の本を読むと分かるが西部は二項対立モデルを徹底して批判し、これを排撃する言論を多用。たとえば、理想と現実とはともにバランスせねばならず現実なき理想主義も理想なき現実主義も最悪だという。
※理想と現実をめぐる結論が僕と西部で完全に一致していて驚いた
したがって、個人主義と集団主義も二項対立モデルで論じるのは完全に無効だという。
まずこの洞察が素晴らしい、二項対立モデルから排中律の設定、帰謬論の発動を介しての独断論を生じる国家編制の知は、このブログでは何回も指摘しているが、こういうカントでいう理性の問題をよく指摘しえている。
いうまでもなく論理実証主義研究者は原子的個人と閉鎖的集団の二つしかないと考えるために、集団主義VS個人主義というバカ論法が生じる。
したがって個人を原子・砂粒として実体化するだけの近代理性の超克が、西部の個人ー集団理論では、なされている。
まとめると、個人主義を第二象限の伝達の自由(差異)と第四の尺度の共有とし、そのために個人は原子的個人と相互的個人の二つの属性をもつ。集団主義は第一の伝達と第三の蓄積の同一にあり、それゆえ閉鎖的集団と開放的集団の二つの属性を持つ。
※個人に関する尺度の単一の普遍性と表現の多様性は近代個人が個性的な個人でありながら同じ人間であるという差異と同一との矛盾的自己同一においてあることを示す
西部は、かかる個人属性と集団属性との組み合わせから日本人論や各国の文化を分析してゆく。
※なお西部は尺度と蓄積の組み合わせを歴史学とする。これは蓄積に対して尺度が物語的な意と時間性を与えることで民族的アイデンティティをなす歴史を構成するということだろう。他にも二つの組み合わせから文学や教育、自然科学を取り出すが、本に何の説明もなく理屈がよく分からず僕が記憶できなかったから割愛する
四象限理論による日本人論
では、結論部分に突入しよう。
まず、大前提として西部は日本の近代化における堕落を問題だといい、日本は近代を無批判かつ度外視に絶賛し、近代への認識と内省を欠き、従米的な思考停止のもと、近代消費社会の大量の模型の大流行に呑まれているという。
モダン⇒モデル(模型)、モデルの流行=モダン(近代)だという。伝統や習慣などのよってたつ規準(モデル)がないまま場当たり的な模型の流行に呑まれるのがよくないと本に書いてあった。
ここでは、そのつど与えられるファッションなどの場当たり的な模型の流行と消費のなかで、拝金主義を拗らせること、つまりあらゆる価値・意味を金という数値に還元し尽くすことの暴力性、経済合理性におけるある種の全体主義を西部は警戒している。
※意味の定量化の危険性は当ブログの色んな記事でやまほど繰り返し論じているから割愛する
したがって西部の言論は、自らの伝統的尺度や伝統的規準を省みることなく、ひたすらそのつどのモードに呑まれて思考停止に陥る大衆を批判する。
批評とは社会の自意識であって、それは自明視され正しいと思われている社会のあり方を否定して、自らの社会を振り返ること、すなわち社会が社会自身から距離をとり、その差異=否定を媒介にして矛盾的同一をなすこと。かかる意味における人々の内省=社会の自意識を喚起する言論を批評と呼ぶ。だから肯定的に自明視された近代消費社会への批判と内省を説く西部の思想は批評の王道をゆく。
※この自己批評精神に西部保守思想の核心がある
本題に入ろう。
まず西部は解放的集団と原子的個人の組み合わせが競争だという。
次に、閉鎖的集団と原子的個人が認識。
解放的集団と相互的個人が協働。
閉鎖的集団と相互的個人が強制。
この中で説明が必要なのは閉鎖的集団と原子的個人の認識なので説明する。
閉鎖的集団と原子的個人が組み合わさると、集団の閉鎖的圧力と個人の自由を求める内面とに葛藤が生じる。この強い集団と個人の差異による葛藤が、自らの存在意味や伝統、尺度、あるいは近代といったものがそもそも何なのかということを人々に問わせる。
つまるところ集団の禁止と個人の欲望との葛藤が認識=内省を実現するということ。
※認識=内省しないのが日本の欠点だ言うのが西部の主張
以上から、日本を協働の国と見なす。そしてそのことが尺度の認識=内省を欠くことの原因だという。
というのも、西部によると近代国家とは民主主義で、これには相互的個人による平等の精神が有利で、また近代の企業ではイノベーションを起こしたりと会社の生産性をあげるのに解放的集団が有利であるから。
というわけで近代と日本人の気質は大変に相性がよく、そのため近代そのものや尺度への認識を欠くことになった、と西部はいう。
また中国やロシアは強制、ヨーロッパは認識、アメリカは競争だという。
ここでとりわけアメリカの競争の洞察が卓越しているので紹介しよう。
アメリカは多民族国家で国家的連帯の構成に、民族性を超えた一義的な価値規範が求められたという、そのため、経済価値(客観価値)による単一の意味の統制が働いて、経済合理性優位の原子的個人と解放的集団の競争社会になったという。
この洞察は経済的価値と意味が客体的価値・一般的意味を構成することをよく捉える。かかる経済審級があってこそ、伝達と経済学とが対応させられるということ。この西部の理論をさらに詰めると、原子的個人の生成と経済価値審級の支配化との連動のメカニズムを読み解くこともできる。
※このメカニズムが意味の差異を巡る誤認と自由をめぐる強迫神経症者の根源的幻想に関わる
西部の象限理論は、いくらでも発展させられるし、扱い方を鍛えればこれで多くを説明できるくらいには使えるだろう。もっとも今の保守派はもしかしたら使い手が未熟でまともに扱えないのかもしれにないが。
しかし、西部の集団個人モデルには致命的な欠点がある、次項でそれを指摘し、西部理論の可能性を探ろう。
四象限理論の欠点
西部が集団主義と個人主義を解放ー閉鎖、原子ー相互の二項に割り振り、これらの性質の一義的な量の多寡と組み合わせによって、集団と個人を論じるのは適切だろうか。
じつのところこれは無理があると思う。
そもそも西部は集団と個人との関係が自他関係にあることを見逃しているだろう。
精神分析における大他者と自己主体との分離関係が、自他の分離、すなわち集団からの個人の分離を構成するわけだから、個人と集団とは何よりもまず、自他関係論として洞察されねばならない。
だから言語を客体的構造とするのでなく、その構造へと主体が疎外(言語化)される水準を洞察しないといけない。西部構造主義では、この視点がスッポリ抜け落ちている。
また、そもそも動物には個人という意識はなく、チンパンジーなどのごく一部の動物を除けば、鏡像すら認識しない。だからこの意味では、動物では主体は個人ではなく種(集団)にあるといえ、人間も言語の習得以前には、種と個の分離はほぼなかったと見なすべきであろう。
であるからには、言語の誕生とその使用における主体と言語との相互関係において、これが環境との関係とも連動しつつ種と個人との分離が段階的に進展したとみるべきなのだ。このような洞察はヘーゲル弁証法や深層心理学の考えの基本でもあり、哲学的にベーシックでもある。
かかる分離の構成は母子関係を軸とする自他関係の分離において記述される。この点は吉本でも精神分析でもユングでもそう変らないだろう。
また、この自他関係論を政治哲学に転移するとフーコーの権力関係論へ繋がる。
※言語がなぜ母などの他者関係に依存するかは他の記事で解説したので割愛する
というわけで、自他関係論=集団と個人との分離の原理論を欠いたこと、この哲学に必須の原理論を欠いたことが西部言語論の最大の弱点であろう。
近代の超克を目指した西部の思想は、このゆえに集団と個人を四つの実体化(独在)した要素の量的な多寡に還元する近代理性的論理へと頽落。
つまり個の生成の原理(自他関係)や個人と集団との関係の回帰的連動が、その言説論理(問題構成)自身によって隠されて見えなくなってしまっているのだ。
※日本人の認識の弱さにおいて本当に問題になっているのは自他関係だが、西部言語論に残留してしまった近代理性的思考様式の効果で、自他関係の水準がその言説自身の影に入って見えないということ、それゆえ中根のタテ社会論と言語構造との連動も見逃されてしまう
いうまでもなく、西部が自他関係論=母子関係・父子関係論を欠いたことで、浜崎洋介の師弟文化論は西部言語論と接続不可となっている。
逆に自他関係論の水準から集団と個人を論じる視点があれば、表現者チームが固執する師弟文化を哲学的に記述し、その思索を深める道も開かれるはず。
※自他関係論と集団と個人の分離の心理学的原理論は当ブログの他記事で論じているので割愛する
なぜ四象限理論は自他関係を逃したか
西部が集団と個人を四つの量的要素の独立の組み合わせに還元してしまった最大の理由は、彼の保守思想が、特称日本論にあって日本国家保守にしかないことに起因すると考える。古事記でいえばクニブリが排除されている。つまり国家・社会を実定化してしまったのだ。
※このクニブリ・場所と天つ神・国家の議論は『哲学する日本』などの山本哲士の本で緻密に理論化されている
これは底の浅い保守派がグローバリゼーションに国家を対立させ、この安直な二項対立でもってことの解決を図ろうとする不毛な状況にも対応する。
説明しよう。
かつての日本の君民一体の統治は全体主義とは無縁で安定していたように見えるが、これは場所制が働いていたため。
つまり近代国家編制における公私未分(集団と個の未分)と場所制における公私非分離とはまったく別なのだが、西部には場所・述語制と国家=社会空間・主語制との言語構造の識別が存在しないため、この水準が見逃されている。
場所制における主客非分離では西田でいう述語的同一性が優位となり、現在性によって集団は柔軟性をもつが、国家制における主客未分(分離の終局)では、主語的同一性(客体の同一律)が優位となり、蓄積が暴力的に作動する。
※場所と国家社会の空間との相違は他記事で解説しているので割愛する
そのため相互性と開放性(協働)、相互性と閉鎖性(強制・全体主義)という組を導入することで同じ公私未分における両者の差異を考えざるえなかったのだろう。
分離が未分を構成するベクトルがあったり、非分離が相互性において安定する古層の言語水準(述語的同一性優位)があったりといった系譜的・動的言語構造論がすっぽり抜けて単一不変の言語編制(国語)で日本語を考えてしまうために、その説明が個人と集団の独立したパラメータの組み合わせに解体されてしまったということ。
不変単一の国語で考えるとこの謎は解けなくなる。
つまり西部の思想は西田哲学の場所論の理解を欠いたこと、あるいはそれをさらに精緻化した山本哲士を参照していなかったことに起因するだろう。あるいはラカンを参照しなかったためといってもよい。
このことから言えるのは西部邁をして、その哲学は西田時代から退行している側面があるということ。あきらかに保守の哲学論理は年々、劣化している。
本を読んで分かったが、浜崎らクライテリオンの人たちより、西部邁のがこのブログの問題意識に近いものを多く感じる。
西部邁とルソーとラカン
西部の構造言語論が提示する第四象限の尺度と一般意志の関係について、これを西部の憲法論の記述と合わせて簡単に補足したい。
西部はその著書において、憲法における国民の総意を‘’現在世代の国民の世論でなく、歴史上の総世代の伝え残せし伝統の精神を意味する‘’と強く主張する。ここで伝統の精神とは、伝統の意志であって尺度に対応させることができよう。
ところで法の究極的な根拠として措定される伝統の精神をラカン派精神分析では大他者の欲望(大文字の他者の欲望)と呼ぶ。大他者には大まかに二種類あるが、ここでの大他者は不在=死者の意を意味する。
さらにルソーの一般意志もまた法の根源的根拠となる精神(意)を意味するのだった。
※西部の日本国憲法における解釈の仕事は彼が伝統とは何かを問うものとして伝統であり伝統の精神を解釈することにあり、大他者の欲望を欲望するものとして自身の保守思想を体現する仕事だといえる
※現在世代の総意はルソーの全体意志(多数決主義)に対応可能と思う
つまるところ一般意志も伝統の精神も、尺度とそう変らず、これらは全て大他者の欲望ということができる。また、カントの啓蒙にしても革命という歴史的蓋然性を心的傾向の必然的きざしとして引き受けて可能となるもので、歴史性(自己同一性)なき近代などありはしない。
ホッブスにしろヘーゲルにしろ、原初的段階では弱肉強食にあって自由・承認を求める人間は自由を求めるゆえの絶対支配と普遍闘争の終わりなき惨状に陥ったという。
このような現在において見出される歴史観に現在自身を組み込むことから近代は構成された。つまり近代をただの過去の歴史からの切断だというのは不正確で、ヘーゲル精神現象学が近代に歴史の必然的連続性を説くように、近代とは過去からの非連続の連続として描画されてきたもので、かかる近代とは近代の内に歴史(過去未来)の意を現在性において解釈する。
そういうわけで大事なのは、大他者の欲望を欲望するとは、法や国民の自己同一性の根拠となる書かれた憲法の行間に国民国家のあるべき指針・意図を、つど人々が解釈してゆくことであり、それは【憲法の架空・不在・死者の書き手=大他者】の欲望を読む(欲望する)ことでしかないということ。
このことから言えるのは問題となるのは大他者を欠如(死者)として構成する社会をいかに持続的に実現してゆくかにある。
さらに西部の問題意識から補足してゆこう。西部の著書によると、彼は現代日本のフェイクニュース問題をメビウスの帯に喩え、内と外、空想と現実の境目がなくなり癒着したせいだ語り、その要因に伝統意識・規範意識の蒸発をみている。
さてラカンも内外、空想と現実、自他の境界を喪失した主体をメビウスの帯によって論じている。
※現代社会がこの境界・差異の消滅にあることは当ブログの他記事で何回も論じているので割愛、ちなみにカリギュラという最近の作品も幻想世界と現実が混ざった妄想世界をメビウスと呼ぶ
じつは、欠如としての大他者(死者)を構成することに失敗すると主体がメビウスの帯になる、というのが精神分析の基礎理論。
※西部のフェイクニュース論も僕の陰謀論について考察したいくつかの記事も社会のメビウス化を指摘するもので、非常に問題意識が近いと思う
このように西部のトピックは精神分析で洞察するとその多くを四象限理論に還元できる。ある意味、ここでは西部論の西部的還元を成そうとしている。
大事なのは、西部=死者の欲望を欲望するにあたっては、四象限理論を自他関係の水準に転移して再構築せねばならないだろうということ。
四象限理論に自他関係を導入することで西部の様々な論説を、西部の四象限理論によって再記述できるはず。
※ただし、それでは四象限理論が独自に切り開いた地平は何かという課題が残される、僕は西部の弟子でも保守でもないから、それについては知らない
西部思想の真髄とフーコーのカント論
ここからが本題であり西部入門となる。
さて、西部邁の保守思想を近代の設計者が一人、カントで論じようとは何事か!という人がいるかもしれない。
しかし、それはレベルが低すぎる。
デカルト・カント・ヘーゲル・ホッブス・ルソーらは近代の基礎理論を組み立てた大罪人として保守派から攻撃される傾向にあるが、そんなんだから保守は、哲学論理のレベルがポストモダニストの足下にも及ばないと言われるのだ。
そもそもヘーゲル弁証法は終わりなき自己否定の運動でもあり、批評する良心を説くヘーゲルの考えは西部でいう尺度を認識・内省して、そのつど具体的に意味づけ行動してゆく、というあり方と大差ない。
ろくに知りもしないで近代哲学=悪という新興宗教みたいな決めつけをしていると、どんどん話がおかしくなる。
※哲学をめぐる近代VS反近代の要因とかもろもろは、後の項目で解説したい
また、フーコーについても西部がもっとも嫌った相対主義をなすポストモダン御三家の一角でとんでもない!と思う人がいるかもだがそれも無効な議論。
解釈によるのか知らないが、フーコーは深く読むならばポストモダンではないし、フーコーの思想は近代の問題をもっとも鋭く暴く。とくにデリダとフーコーはまるで別物、まったく格が違う!
ポストモダンでは近代哲学批判がミッションになっているが、ポストモダンとみなされがちなフーコーはカントの自由が主体化=従属化である点を危惧する一面もあるが、肯定的にカントを評価。フーコーの哲学の読みは高度で、カントという主語を外して、その啓蒙哲学を思考プラチックー言説プラチックと自己技術ー統治技術の水準で読解するのが特徴だ。
ちなみに、フーコーはカントの啓蒙哲学を評価し、この啓蒙の主題を20世紀に再び取り出した人物にカンギレムの科学史をあげる。フーコーはカンギレムなくしてフランス現代思想なしとまでいう。カンギレムは合理性そのものを理性において問い、誤り=偶然性=断絶=差異の哲学を知・合理性・概念の水準で提唱し、近代主体・経験・意味の近代哲学に対置させた。
※僕のフーコー理解は山本哲士のフーコーの書籍に依拠しており、この記事のフーコーのカント理解も山本の著作『ミシェル・フーコーの思考体系』に依拠する。ちなみにまだこの本は読んでる途中。フーコーは深層心理学の論理を社会科学領域に転移するのに最適
カントの哲学と啓蒙と批判
※この項目、かなり冗長になってしまいました
さてカントの哲学は啓蒙と批判にある。
啓蒙とは西部が保守を具体的理念を持たない態度だといったことと同じで具体的な何かではない。それは自己批判という態度を示す。つまり自己が自己からズレ続ける自己差異の哲学を構成する。
カントの場合、西部とは異なる仕方で、つまりフランス革命という歴史の外在性を受け入れることで、啓蒙=『啓蒙とは何か』を実現している。啓蒙の哲学は啓蒙とは何かと自らの現在において自らを問うこと(内省)にある。啓蒙では正義や良心の意識、法や規則に従属する主体、自由に考えるということ、これらの関係性が問われうるが、その本質は現在において自己とは何者か?を内在的に問う自己技術にある。
カントは革命の成否と無関係に、革命において人々が自らの選択した政府をもって政治的戦争のない平和を目指した、という心的傾向があることを受け入れ、これによって啓蒙の内在的な自己批判の運動を確立した。フランス革命は偶発的な出来事であったが、そのつどの偶発的出来事はそれとして重要な意味をもつのだろう。
つまり革命という外在的な偶発的出来事を自己の良心をめぐる心的傾向(必然)として引き受けた(解釈した)ということ。
この啓蒙に付随するのが実践理性批判や純粋理性批判などに示される自己批判の精神。
カントの哲学(啓蒙)はそれゆえ、現在性・内在性にあり、この現在において歴史(過去・未来)を意味付けその歴史において自らを位置づける。これにより自らの哲学の意味と目的(啓蒙とは何か・自己とは何か)を自らの現在の内に見出してゆく自己言及の差異と同一の運動をなす。それゆえに自己がなんであるか?を現在において問う自己差異の批判哲学なのだ。
※私が私の現在において私の現在を根拠に私の現在を問い、意味づける、このとき問う私と問われる私との差異が生じ、この差異が自己同一性に対して常に運動を要請することとなる
批判とはだから具体的対象ではなく、知っていることや正しいと思っていることに対するそれ自身の差異を構成する内省の機能であり、態度・現在性ということになる。だから僕の理解によると啓蒙自身の自己差異が批判と呼ばれている。よって啓蒙と批判との差異がカント哲学における理性・合理性の過剰な統治からの自由を実現する根拠となっている。
※この啓蒙と批判との差異を超える自由プラチックとして晩年のフーコーは古代ギリシャのパレーシア・自己技術を見出す、さらにパレーシアからヘレニズム期の自己への配慮へと検証対象が広がってゆき、自己放棄と原罪のキリスト教的な自己技術の変質の理由がさぐられてゆく
このようなカントという主語を排除して可能となる言説の実際行為(語ることで生じる語る主体の意図を超えた効果)の水準と自己と自己との関わりの技術という観点からの読解によって、カントの近代哲学の内にその近代性を超克する原理を抽出可能となる。いわばカントの意識ではなく、その無意識(プラチック)を読解しているのだ。カントに内在する非カント主義を洞察するということ。
補足すると『革命とは何か』という外在性を引き受けて『啓蒙とは何か』という内在性の哲学を実現ししている。
さて、カントという主語において読むと、その哲学は、純粋理性批判のアンチノミーによって真理の形而上学の限界を露呈し、その人間主義的な相関主義において、新しい道徳根拠の探求領域を開拓、これによって道徳を神などの超越的存在から切断し近代を構成したとみなされるが、これではカントが近代の内に近代を超克する哲学を内在していることが見逃されてしまう。つまり近代という基盤がどのようなものか見えない部分が生じるわけだ。
※このカントの通常の読解は近代哲学派の王道のカント論
繰り返すが、カントは、人間の認識と理性の限界を自己超越的(自己言及的)に取り出し、自己差異を構成することで、このようには統治されないことを実現し全体主義へ抵抗する、それがカント哲学の批判の現在的意味。カントは道徳における主体の従属化においても、その根拠を人間理性にもってくることで、理性に対する理性の自己適応(批判)をなし理性の限界を晒す、これによって過剰な服従から解放されることを、安定した服従において実現する。
カントのいう自由とは従って理性に対する理性の行使で、それは理性を批判して問いにふすこと。理性の限界を晒し、何を知ることができないか、を理性において暴くこと。それゆえ個人の自由は普遍的理性・合理性に対する理性への行使においてであり、そのために公的場面において人は自由に考える個人主体となることができるわけだ。
逆にもし、理性が即自的であれば、人は理性と同一化しており理性・合理は無欠の法とかすだろう。この場合、人は合理性の奴隷となり、その理性の判断を変えることも疑うこともない。理性による真理がもたらす過剰な権力のもとに隷従するだけの主体となる。
だから普遍性をなす理性にたいする理性の行使、理性自身の自己差異は、理性に自由に主体的に従属することを意味し、それが自由だということになる。
※ラカンの大他者の欠如の構成と理性に対する理性の行使は近い、理性と知の限界を知ることはラカンの去勢に対応する
重要なのは、ここでカントの啓蒙哲学が、自己とは何かという自己関係、理性による真理の限界(物自体は不可知など)の暴露、さらに道徳における権力・統治と自己との服従関係、この三領域をめぐる啓蒙と批判の自己技術にあって、主体、知、権力の三つの水準において自由プラチックを実現すること。
※フーコー三角形の順番は知⇒権力⇒主体からまた知へ向かう循環にある
かかるカントの批判哲学は歴史上、統治の一般化が背景にあったが、統治の一般化とは科学的真理や教会の真理において教育や経済、政治の合理的記述が、人々を過剰な権力のもと服従化してゆくことを示す。このような統治の一般化にあってカントの批判哲学があり、それは「いかにそのように統治されずに済むか」をなす。統治の一般化と批判はセットだったということ。
さらにいえば近代国家では、キリスト教的パストラール権力における意識への隷属、告解において内面を余すことなくさらし、その告白において言語的意味へと自己自身の全てを還元せよ、という個人化における全体秩序(言語)への隷属が問題にあり、この過剰な権力からの自由をなす、これがカントの哲学の自己技術であり、批判の今日的な歴史的意義となる。
※この告白における自他関係(師弟関係)でなされる内心の意味化の暴力が、西部でいう数字=経済合理性に還元し尽くす近代の暴力に対応する
※キリスト教にある告白は悪しき想念・隠れた肉欲(症状)を全て言語化し、内面の全てを言語化する義務によるがこれはフロイトの精神分析に似てて、ラカンの男の式であり強迫神経症者の疎外(言語化)に対応するはず
そのため、批判には三つの歴史的準拠点があり、聖書の批判、法の不正に対する権利の確立、権威が真理であることの批判と科学の三つが統治の一般化とそれに抵抗する批判化の二つを同時に実現する。
またカント哲学では道徳主体(精神の自由)と認識主体(外的対象を認識する主体)との分離が問題にされ、これを統合する普遍主体が目指されたが、僕の解釈ではこれが、前述した意味の存在論的差異(分離)の成立に関わっている。つまりこの二つの主体の差異・葛藤の自己関係が道具的意味(現実言語)と一般的意味との差異の同一に対応する。
そしてこのことが、実践理性批判における自己を律する理性の普遍的使用、公的使用における個人の自由に連動している。
※実践理性批判での汝の格率が他者一般の格率に一致するようにしろ、的な言説も集団関係において個人の自由が生成されることを示す、これはカント版の自由の相互承認かもしれない
※カントは嘘論文が有名だが、絶対的正しさを具体的に規定してしまう欠点もある
カント=西部邁と自裁死の問題
西部といえば、既に確認したように二項対立で考えるのを否定するのだった。二項対立は近代理性がよくやる思考法だが、これは西部式の純粋理性批判と解釈できよう。
純粋理性批判はカントの三大批判書の一つで近代理性による思考を徹底するとアンチノミーとなることを論証して、近代が絶対視する理性の限界と誤謬を暴露したもの。
具体的には自由意志はあるともないともいえないとか、物体に最小の構成要素を措定することはできないとか。つまるところ近代理性に典型される線形因果思考の矛盾を指摘するものが多い。
また西部はその著作で現在性において、伝統の具体的な意味を自分の頭で考えよ、というニュアンスのことを言ってる。これもカントと同じ。ようするに西部保守とは過去への回帰を言っているのではない。
伝統を重視し、そこに慣習を絶対視しないまでも一つの規準と見なすとはいえ、つねにその問題の中心には現在がある。つまり現在において歴史を意味づけることが成されている。
ひたすら過去に帰れと叫ぶだけの全体主義予備軍の古典主義ではない。
何より、西部は自に保守の現在的意味と意義を問い打ち立て、自らの現在において自らを語るという仕方でその哲学を開いている。つまり西部の哲学は『保守とは何か?』であって、それは西部版『啓蒙とは何か?』に他ならない。西部の関心はその著作を読む限り、現在のただ中にあって、保守とは何者か?自己とは何者か?を徹底的に問うことにある。
であるから、西部のテキストはその性質上、死ぬことがない。
テキストの欠如としてある根拠、つまり書かれたテキスト=表現(第二象限)の根拠となる尺度を読者の現在において問うことが求められている。西部における西部への内在的批評がその読解の作法として要請されている。
であるからこそ、終わりなきテキストの再解釈による自己差異を実現することが保守ということになる。これは前述したカントの啓蒙と批判の哲学とそう変らない。
まとめると二項対立批判は西部版純粋理性批判。また個人主義の構成要件とされる多様な表現が単一の尺度においてあることは、カントの理性の公的使用による個人の自由の実現に相当する。両者はともに、自らの現在において歴史・伝統を意味付け、自己自身を問い、自己差異を構成すること、内省を重視しており、この内省のために蓄積と尺度との分離や二つの主体の分離への葛藤やアンビバレントが生じている。
また西部の認識の成立の論理もカントの認識に対する超越論的哲学に対応させることができるかもしれない。どちらもが超越論的視座(自己差異)を核とするといえなくもない。
そもそも認識と尺度を保守思想として重視してるわけだから、その時点で凄く近代主体だと思う。
さて、カントと西部はその欠点をも、同じくするかもしれない。
カントではせっかく開いた道徳の主体と認識の主体との差異を、最高善によって埋め立ててしまう。
つまり最高善において彼岸に神を要請することで、内面精神の自由と外界物質の充足=徳と福の絶対的一致を幻想する。
※ヘーゲルのカント批判はここにある
これはもちろんラカンでいう根源的幻想の見本というべきもので、この幻想が生み出す誤認への無自覚が近代の暴力性=全体主義を構成する。
※この誤認と幻想による近代構造の自壊については当ブログの他記事で詳細に論じているので割愛
これと同じ事が西部にも見られるかも。
西部邁といえば自裁死したことで自己の生を意味づけたのが知られるが、これは著書を読むに生権力への抵抗だったようにも思える、西部はひょっとすると、戦中における民族=種と個人との一致における死の権力にどこが望郷の念があったのかもしれない。
西部の本の最後に自分の自裁死についてと病院批判が書いてあって、その前の項目で学校批判と自分が学校からエスケープしてきた人間であることが書かれていた。病院も学校もフーコーが近代構造として問題にしたもので生権力の中枢となる。
※これだけ痛烈な国家編制批判の感情を吐露しながら、これらが国家に属することが西部では見逃されている、国語に関するくだりなどはとくにそれを感じた、言論に捻れがある
※もし国家と場所との言語論を知っていたら西部の言説はまったく違ったはず
※僕は反国家ではなく国家と場所の二重性が必要だと言っている、マルクス主義に典型される反国家はそれ自体が国家編制に過ぎない
またチェスタートンを引用して、一つの良き思い出、友、女、本が大事だといい、現代の平和な世界では良き思い出や友が一番得るのが困難だと語っているのだが、その理由に戦争の不在(平和)を挙げている。
つまり、共同体を守るための命がけの敵との闘争というドラマティックな生の意味の共有がないために本当の思い出や友を得るのが困難だという。このラジカルな帰結は西部に固有で現代人でこれに素直に賛同出来る人は少ないだろう。それゆえ、この記述には西部に固有の欲望がよく現れている気がする。
どこか戦争(心的外傷)のような種と個との融合が西部においては、喪われた過去の彼岸として望郷されている気がする。
※フーコーは近代以前の古い権力は死を要請するものだったという。ここでは民族は一つの共同幻想のもとに共同的な死へと向かい生を意味づける。死は共同幻想としてあって、生の目的は戦死にあったのだ。たとえば戦中日本の特攻では靖国という共同幻想のもと死がハイデガーのいうような個人的なものでなく共同的幻想として捉えられ、天皇権威は途中から国民の死を要請した、死の共同性において種が個を呑み込み個は種として自他の一致の享楽に至る。生権力は死後幻想の解体に伴うもので、これが西部のいう故郷喪失と呼ばれるものの条件であろう
※西部の本では近代産業社会によって故郷喪失感が生じることを問題視する文章が大量に出てくるが、喪失において言われる故郷は自他の一致、つまり蓄積と尺度との一致、意味と意味との一致、言表と言表行為との一致をなすウロボリックな世界に他ならない、したがって西部のいう故郷とは心的外傷としての戦争体験に他ならないと思う
いずれにせよ、差異を開き、その現在性において自らの自らへの逗留を拒み自己差異の思想プラチックをなした西部は、その近代主体性の効果として根源的幻想を抱いていたのではないか。それゆえ故郷喪失感は、西部思想のうちで中心的な役割を演じているのかもしれない。
かかるカント=西部邁の思索は近代主体を超克しうるもの、つまり近代がその構成条件として反近代=近代批判を内在することをよく示す。と同時にそのような内在的近代批判の原理が、彼岸における自己差異の静止、自己との完全なる静的一致の幻想を構成することが示唆される。
補足すると前述した言語の意味の存在論的差異の同一において、道具的意味が一般的意味だという誤認が構成されるが、この意味の誤認を構成する核となる欲望の中核にあるのが、根源的幻想=エスバレ・ポワソン・プティットアーとなる。
自己が自らの現在において自らを何者なのか?と問うこと、この終わりなき問いの運動が保守思想の核心となるだろう。すくなくとも哲学の論理として西部を読解するとこの解釈は避けようがない。認識と尺度、態度の保守思想とは啓蒙と批判のカントと紙一重なのだ。
現代の哲学者の鳥瞰図
さて、西部邁は全体的見晴らしをえることを重視していたから、思想についてそれをやって見よう。
まず今の哲学シーンでは近代派VS反近代派で断絶がある。近代をどのように認識するかで哲学の立場が決定するといってよい。
デカルト、カント、ヘーゲル、フッサール、ホッブス、ルソーの評価もこの立場から決定しがちだ。
※とくにヘーゲルの賛否は近代にたいする評価で決定する傾向が強いが、他の哲学者については一概にいえない、たとえば近代の問題点を指摘するフーコーもカントについては既に示した通りの高評価を与えており、またポストモダニストでもルソーを評価する論者は多い
これら近代哲学の創設者たちは、哲学のミッションである普遍的知の構築を目指している。デカルトは方法的懐疑において疑いえない意識の場を措定し、カントは普遍的道徳の法則をたてようとし、ヘーゲルは普遍的真理の弁証法の運動による動的一致を、フッサールは相関主義による普遍的知の合意的な構築の手法を提示した。
普遍的規範を神などの超越的存在や物語に頼らずに、つまりニーチェ的に本体論を解体しつつ、現象学的に構築して社会を安定化させること、これが現代の近代哲学派の核心となる。また近代派は近代の資本主義による格差問題もヘーゲル(一般福祉)+ルソー(一般意志)で乗り越えようとする。
これに対して、近代消費社会の格差拡大の矛盾やマルクス革命やナチズムのような近代における普遍規範の確立に起因する全体主義を問題視するのがポストモダンであり、彼らは近代哲学を否定して、普遍的規範・基準(クライテリオン)の否定による相対主義を主張する傾向がある。
また、マルクスガブリエルは僕の理解だと相対主義によってその規範を多様化・増殖するポストモダンの亜種に見える。
全体主義は特定の規範(第三象限・蓄積)がカチカチに凝り固まって、その規範に誰も逆らえない閉鎖的集団を構成するわけだから、そういう規範の絶対性・普遍性を帰謬論をつかって解体するのがポストモダンの手口といえる。
いわば伝達を蓄積や表現から引き剥がそうという画策がポストモダンにはあって、そのためにスキゾキッズの逃走とかアイロニーとか発達障害のアート論だとか、スキゾイド・スキゾフレニーや発達障害・非定型発達に依存した理論が多い。
※誤認に起因し国家編制における主語的同一性において蓄積と尺度との差異が消滅することで蓄積が伝達を支配する近代全体主義が構成される
たとえばポストモダンのデリダは『声と現象』で現象学批判・パロール批判をなすが、その手口は現象学における意味作用と根源的今の否定にある。意味作用は、たしか現在における直接的な意と言語的意味との一致の内的確信の感覚などのことだったはずで、これをデリダは、ゼノンのパラドクスにあるような時間の今の空間化=デジタル化によって解体・消去してしまう。
※時間は客体化すると無限のパラパラ漫画に解体されて、その連続性が解体し、今が消滅する、だから現前に根拠をとる現象学では、今は広がっていてそれが今のうちから差異化して過去未来が析出すると考えがち
つまりデリダにおいては、意味の一致の確信も、それを自覚したときには、痕跡に過ぎず、一致の確信感覚には遅延があって一致はない、という感じだろう。たとえば美味しい!と思い、これを自覚するとき、美味しい!という過去の痕跡との一致が確信されるだけ。言い換えると、美味しい!と思ったと思ったと思ったと、、、と思う、というように思う私(超越論的自我、存在)とその思いの自己認識(経験的自我、存在者)とで時間的にずれ込むという感じ。
※最近現象学系の本を読んでないから、うろ覚えだが、たしかこういうロジックだったはず、ゼノンのパラドクスにおける時間の今の問題は浜崎が講演で語っているので、塾生にはこれ以上は説明はいらないだろう、このブログでも他の記事で解説している
もちろんこれはベルクソンやハイデガーの議論からも分かるが、レトリックに過ぎない。デリダの有名な差延も現象学における根源的今・現前の確証性を解体するためのレトリックと考えられるだろう。
後の項で確認するが、現象学批判がポストモダニストには強い。
※認識主体・意識というデカルトの系譜にある現象学との対立関係は重要
もう少し分かるように具体的に見てゆこう。
保守派の哲学論理
まず、保守派は近代を否定するのでデカルトもカントもヘーゲルも雑に否定する傾向がある。これだから今の保守派は哲学が弱いと見なされがち。
すでに示したが西部の保守思想はそもそも近代主体にあってカントのそれともっともよく一致する。近代に内在する反近代の哲学だ。
かかる保守派は近代を規準(モデル)も基準もない、つまりクライテリオンなき相対主義の怪物とか、定量化された科学の知による全体主義の権化と見なす傾向がある。
このとき後者の問題意識はポストモダニストとも近代哲学派とも一致する。
またこの問題提起のうちには人中心主義、主語中心主義による、過去を断絶する未来志向的設計主義への批判も込められる。それゆえ古い基準を解体するポストモダンを激しく批判するのだが、その問題意識には共通点もあるわけだ。
※たとえばポストモダンの影響下にあるモダンアートは伝統的な美の基準と規準を強迫的に破壊することを使命とする
しかしまともな保守は過去に帰れとは言わない、西部も言わないし浜崎もそれはありえないという。当たり前で、過去に戻るということは現代の文明的暮らしの完全な放棄と学問の死に直結する。
※古典主義系の保守は過去に帰れと言い出すし論理もまったくないので困る
まとめると西部保守は、近代的近代批判をなし、近代におけるクライテリオンの消失に見られる相対主義を問題視するとともに、近代の主語主体の構成と経済合理性や統計学などの科学的知における数字の暴力を問題視している。
※こうして観ると意外にもその問題意識はフーコーに近い、そのためか西部は本のなかで学校批判をするのにフーコーの術語ディシプリン(学問教義)を使っていた
保守派の三つの要点を示そう。
①クライテリオンの再構築=相対主義を克服
②近代主語主体を批判する一面あり
③科学的知の過剰とその真理による全体主義化の批判
表現者系の保守は国家や学校、定型的基準・規準を肯定するので凄く近代派っぽいがカントやルソー、ヘーゲルを単純に全否定したりするので、言論に混乱や捻れを感じる。カント的でありつつカントを全否定したり、国家編制批判的なのに国語ー母語論で教育と言語を語ったり極めて混乱した言説が目立つ、そのためうまくまとめるのがもっとも難しい。
ともあれその要諦をここに示せば、
近代において砂粒化した個人が、他律技術の家電製品によって全て個人で自足できるとはき違え、そのことで甘ったれた無責任の主体が台頭。その結果、自己責任やら自由やらが称揚され、旧来の秩序や共同体のしがらみ、とりわけ師弟関係が自由の敵として一蹴されて共同体の解体に至る。これが現代日本の問題だと考えているようだ。
保守派は現代日本の問題を西洋型の個人主義を甘ったれたものとはき違えて輸入したことにあると観ており、これは京都大学の河合隼雄の永遠の少年元型をベースとする日本論に通じる。また河合隼雄は父性なき日本で日本的な父性(クライテリオン)を立ち上げようとした臨床家として知られるが、やはり表現者クライテリオンの振るまいはフロイディックであり父性の屹立を画策している側面が強い。
このとき父性とクライテリオン・基準をめぐる考えの違いが、ポストモダニストや現象学派と保守派を分かつ最大の理論的な違いとなる。
デリダを神殺し、父殺しの子の論理とすれば、表現者は死んだ父を回帰させる術を探り、昔の日本の師弟関係=他律技術にその手がかりを探っていると見なせる。
※フーコーでは古代ギリシャに自己技術が探られたが表現者では昔の日本に他律技術が探られてしまい、やはり捻れがある
ここで重要なのは、保守派が戦後の日米関係に日本の甘ったれた勘違い個人主義の原因を取り出していること。
ゆえに表現者の安全保障論も日米関係論もクライテリオンの再構築も、父性の死という問題意識に帰結する。
※戦後の日米関係と個人主体の問題については当ブログの攻殻機動隊SACを評論した記事を参照して欲しい、この記事を読むと藤井聡や浜崎が日米関係論でいいたいことがよく分かると思う、さらに僕の論考では核兵器がファルス=国土=国体と関わり、これを持つことが国民国家の自律を構成する心理的布置を形成すると考える、核兵器などいつかは消した方がいいと思うが、今は核保有=ファルスを持つことを検討しつつ、核シェアリングのあり方をアメリカという単一の父の名とするか、複数形の父の名とするか、その意味と布置をよく分析するのが善いと思う
ポストモダニストの考え
現代のポストモダニストは國分、千葉、松本の三名に代表されるだろう。遡ると浅田彰が日本のポストモダンの火付け役とか。
彼らがその思想で標的とするのは、近代主体に他ならない。保守派と同じく主語的主体(受動態ー能動態)が最大の敵といってよい。とりわけ近代主体がその誤認において強化する自己同一性を問題視しているのだろう。近代の自己同一性が全体主義的な規範化を蔓延すると見ているように感じる。
※現代のポストモダニストのが保守派より理論的な完成度はやや高い印象を受ける
したがって彼らは、主体を構成する近代哲学を的にかける。
これはデリダが根源概念の否定と普遍性の否定のためにフッサール現象学=近代主体を批判したことに通じる。
つまるところ現象学とは、一切の認識・現象を個人主体の意識や体験に還元し、その意味や動機を主体・意味に還元するような雰囲気がある。この主体の構成はデカルトに始まる。デカルトによって近代西洋哲学の認識の主体=主語が本格化し、このデカルトの哲学理念を嫡出子にフッサール現象学は相当する。
ここで注意しないといけないのがハイデガーの位置づけだ。ハイデガーは一般に反近代の名手として名高く保守派の哲学の担い手として、保守派から絶賛される傾向にある。西田との類似性の指摘も多い。
※ハイデガーは主体と客体・環境との分離を嫌い、現存在と存在者、世界内存在という主客非分離のパースペクティブを導入して近代西洋的な主体論を克服しようとしたが、しかし西田が到達した場所の水準には届かず世界内存在は社会内存在に留まる
しかしハイデガーの哲学は、近代主体の系譜にある。だから初期ハイデガーを現象学派=近代哲学派は肯定する傾向がある。当たり前だ、ハイデガーはフッサールの弟子で、その存在論はじつのところほぼ現象学なのだから。
※フッサールに欠けていた欲望相関性の視点が存在論にはある
ハイデガーでいえば、気遣いに基づく存在(あるということ・行為的意味)が、そく自己の実存(主語主体)へと接続されるが、このような実存を持つのは近代主体の特徴となる。存在が即、主語の構成にいたる存在規制を普遍的人類のあり方として措定する、つまり近代主体を普遍化しているのがハイデガー。そのため近年、日本のポストモダニストはハイデガーを定型主義として的にかけだしている。
たとえばアニミズムであれば対象の側が存在の主体となってくる(物の魂・霊など)から、ハイデガーの実存の論理は人類に普遍ではない。
そもそも死の先駆だとか不安を根本的情態性に据えるところも近代主体的。後期のヘルダーリンへの陶酔しかりで、否定神学構造にある近代主体の臨界点にハイデガー哲学はある。
※死後幻想の消失=イメージの否定、において死の個別化=ハイデガー的な死と不安が可能となり、これは近代に特徴的な事象となる、ユング派などの深層心理学ではハイデガー=近代主体は昔から指摘されている
※ただし、フーコーが指摘する古代ギリシャの自己技術をなす自己への配慮における四つの習練の最後、死への瞑想・死の行使ではハイデガー的な死の先駆における一回性の生の意味付けがなされ、キリスト教の自己技術と対比させられる。ハイデガーの死の論考には同時に近代以前の自己技術の水準があるともいえるだろう
そのため主語主体の解体を目指すポストモダニストは、ハイデガーやニーチェに見られる近代的な気遣い相関、欲望相関を否定して、現象学的指向性のない新しい主体(脱主体)を中心とした哲学を提唱する野心に取り憑かれている。この野心はかつてストローマン論法によってフッサールを否定したデリダの現象学批判を近代主体を標的にリバイバルしたもののように僕には見える。
この哲学的野心が近年我が国で急増する発達障害の当事者研究として進められているのが現在のポストモダニストの最新の動向だ。
ようするに近代が構成する根源的幻想を核とした欲望の誤認における自己同一性の硬直化にこそ近代の本質をみてこれと断固闘争するのがポストモダニストだといえよう。
※自己同一性は自己とは何者かという真理の構成の問題に直結し、この真理をめぐって権力関係や統治性、科学などの知の編制、自己関係が密接に関与すると考えるのが初期の【真理】ー権力ー主体のフーコー三角形の考えとなる
※厳密にはポストモダニストは誤認の問題には気づいてないっぽい、気づいていたらもっと違う考えになると思う
ポストモダニストはヘーゲルやカントが、近代の本質を、その自己否定性の運動に見出したのとは異なる見方をしているということ。
とくにヘーゲル批判にあることが近代派との対立において重要で、その意味は歴史の連続性=自己同一性の扱いに関わってくる。ヘーゲルは主客未分離の太古的な人間精神が歴史的な運命的発展にともなって、主客分離にいたり、さらにその分離が、ヘーゲル精神現象学によって結合と分離の結合という動的弁証法関係に至ることで歴史が完成(弁証法がスタート)するという単線的な精神の発展史観を構成する。この単線的な歴史のアイデンティティそのものが、近代主体的自己同一性の発展的系譜に対応しうる。
※フーコーの場合は古代ギリシャの自己技術のエクリチュールに属する二つの書法、覚え書きと書簡の考察がとくにわかりやすいが、可能性として複線的でありつつ種別的な統一性を偶発性において持つ自己同一性(主体)を、近代を超克する自由プラチックとして考えている、フーコーは思想的にはヘーゲルとは対立的な関係をもつと思うが、しかしデリダの脱構築と同じにされるのを嫌った、フーコーはポストモダンではない、この書法は後述する本の読み方を考える上で興味深い
※ヘーゲル歴史観は後のフロイトの系統発生的な心的理論にも見られる、たとえば縫いぐるみに主体=魂があると思い込む未熟で幼い子どもは未熟な古代人の心性を系統発生しているという考え、これと関連してプラトン(正嫡主義)のイデア想起説とフロイトの欲動論も似ている
※余談だが木村敏では人類の精神の歴史展開を癲癇⇒統合失調症⇒双極性障害(躁鬱病)とし、ハイデガーを統合失調症の水準で読解する、僕なりにこの先を綴ると躁鬱病⇒発達障害と歴史規定できる、木村敏は亡くなったがその理論は生きてその続きを自己生産し続ける
このような弁証法的進歩史観的な側面を肯定する場合には近代主体は自己否定による肯定を迫られる。このヘーゲル弁証法史観を否定して、近代主体を退けてゆくのがポストモダン。だから近代主体(近代構造)をそのまま否定するか弁証法的に肯定(批判)するかは歴史をどう捉えるかにも直結してくる。
この視点が抜けるとなんで竹田青嗣や苫野らが現象学を近代哲学の一つの達成点として強調するかもわかりにくいかも。
大事なのは現象学派は、定型的主体において構成されたもので、定型的自己同一性の止揚をなす、このゆえに必然的に歴史観がヘーゲル的側面を帯びうるということ。
※哲学系のネオ高等遊民の苫野批判が的を外しているのはこの点を見逃しているため、現代社会問題の現在性と定型をめぐる主体論から捉えないと本質をつかめない、実践的哲学ではかならず現在性における歴史規定と哲学の意味の規定というカントの啓蒙の主題が入り込むが、ネオ高等遊民は実践と言いながらその現在性を排除する批評をやらかしている、哲学のアクチュアリティを見逃しているということ、YouTuberレベルと思う
ポストモダニストはしたがって歴史の同一性のあり方もまた、発達障害に見出そうとしている節があるかも。つまり連続せずに場当たり的に逃げてゆく今の重ならない集積に歴史を還元しようということ。
※ポストモダニストのヘーゲル批判=近代批判では、ヘーゲルには、さらなる歴史の発展のためにあらゆる否定が同一化される暴力があるという。松本卓也などは、こうして同一化=意味化のための贄とされてしまう差異(無意味)の生け贄化を問題構成する。ヘーゲルの芸術の終わりの論考はこの意味での言語的な意味水準の優位性をよく示す。象徴的意味に奉仕するだけの現実界といったニュアンスだろうか。僕は、この批判は有効だと思うが、一概に否定するのも無効で象徴界の二重性を考えないといけないと思う
※フーコーだとヘーゲルと対蹠的で同一より差異が注視されるため現実界の水準が強そう
まとめると、ポストモダンは、
①主語主体の自己同一性を否定
②差異の相対主義を形成
③近代主体⇒発達障害への主体のレジームチェンジ
ポストモダニストの中心的問題意識は近代主体がもつ自己同一性の暴力、主体の硬直的な一般的意味への従属化にある。すでに他記事で書いているから詳しくは割愛するが、ポストモダン相対主義は、完全な一致以外を一致と認めないということにある。だから差異の同一が構成されず、一般的意味=蓄積(第三象限)へと表現(第二象限)を重ねてゆく伝達(第一象限)の自己同一を拒絶し、主体化を解除する反主体化=反言語的意味化の哲学を構成する。
これはポストモダン相対主義が客観であり絶対的真理(物自体)の位相を不在という資格で絶対化する主観客観の二元論パラダイム=近代理性の水準にあることを意味する。
また近代主体は近代国家の相関者であるから、ポストモダンでは反国家という含みもある。
※近代理性批判を近代理性の内側でやってしまう不毛さがポストモダンの最大の欠点で形而上学批判の形而上学というより他ない、この不毛を超えてプラチック分析=述語分析の境地を開いたのがフーコーで、思考基盤がポストモダンとフーコーではまったく違う
※主体が差異=欠如を排除するポストモダン思想と商業主義との親和性は当ブログでソーセージパーティーやバービーといった映画の解説記事で触れている。ポストモダンは主体を人間から商品・象徴へとしわ寄せし、商品が魂を持つ時代
※このポストモダニストの逃走とかスキゾキッズ論を僕は一概に全否定まではしないが、これで解決するほど甘くない
つまりポストモダンでは、近代編制の内側で近代主体批判をする不毛な論理構造が問題となる。そのためにマルクスガブリエルのような帰謬論をつかったふざけた論証が多用される。
またポストモダンを相対主義でけしからんといっても、彼らはラカン派などの臨床に精通していて、この現在の世界でとくにティーンエイジャーの心がどのような構造変質を生じているかを熟知している。
僕自身もZ世代を観測してきたが、現代人の心であり言説の構造はポストモダン化していると解釈せざるえない。
事実、僕が述語制の論理を主張してもどうしても現代人には理解されない。そもそも現代人は内省構造をつくりだすことができない。ふざけた院生と話しても分かったが、言説から内省構造が全て消去されている。ジジェクで言う禁止の禁止が暴走して人間が猿になった。
このディスクールの動態構造は強力で、保守派が考えるような甘いものではない。
したがって必然、ドゥルーズなどを示すのがベターという事態も生じる。個人の知能の問題ではなく拒絶されて線形論理(ポストモダン)以外の論理が排除されてしまう。
ともかく最近ならネトフリの『新幹線大爆破』とか見ても分かるが、もう定型的父(師父)を立てるのは現実的ではない。この考えはヘーゲルを肯定する現代ユング派ですら共通している。
さて、塾生向けの話だが表現者の早稲田講演の動画で、講演者の一人が浅田彰のスキゾキッズの逃走を雑に否定していたのでそれについて示そう。
ポストモダンの正当性はトランスジェンダーを見ているとよく分かる。たとえば佐藤かよは、最終的に自分の男女の性別への固執から離脱し、ラカン派でいうサントームの単離(スキゾイド的なあり方)を自力で実現した。ここでは主体は単独的なものとして自認されて言語的意味への還元を退ける。つまり意味から単離される。この生の決断を批判する権利は何者にもないだろう。男女の規準を押しつけるだけでは解決しないということ。
※サントームの単離は規範や象徴を否定するのではなく、その差異を引き受けることだと思う。デリダ的に差異を指摘して象徴・規準を批判しだすと攻撃者への同一化が起きて規準が増殖、西部で言うモデルの大流行となる
※保守派は一般的意味、統計の暴力を否定する一方で、なぜかポストモダニストのスキゾイド論を全否定する、ちゃんと異同を理論的に把握した方がいい、保守派は一箇所でも考えが違うと発狂して全否定する印象が強い
つまり意味化への抵抗が今日のポストモダニストでは主張されるが、このとき重要なのは差異を引き受ける仕方をとるか拒絶するかで決まる。デリダのロジックだと差異が拒絶されているに過ぎないと思うが、ラカンのスキゾイド論には差異を引き受けてよりよく自己を生きる水準があるのだ。意味化に対する態度のこの微妙にして絶対的な違いを無視して雑に否定してもまったく無効である。
この意味外の自己存在の単独性、つまり佐藤かよでいう私は男でも女でもないと一般化を退ける自己認識は、ヘーゲル弁証法においては隠されてしまう水準となる。この点が現在において近代哲学派とポストモダニストのヘーゲル論の対立を考える上での一つのポイントになりそう。
ともあれセクシャルマイノリティに観られる生の事実はポストモダン派の根拠となりうるだろう。
※僕はポストモダンは支持しないが象徴界のぶっ壊れた現状からするとスキゾイドが重要な局面があるのは疑えないと思う、差異を引き受けるための単離はとても大事としか言い様がない
思想哲学はまったき生の現実に向き合ってそれに耐えうるよう、つねに一切妥協無く鍛えねばならない。僕が保守派に疑問を感じるのは、こういう姿勢を欠いて映ることがあるからだ。
理論生産が非常に重要な局面に来ている。ここでどれだけ卓越した理論生産をなしえるか、いまが勝負時なのだ。保守派の塾生も自分でどんどん理論生産しないといけない。師父に従うだけでは話にならない。塾生が自律して自分で本を読んで理論生産をしないと新興宗教と変らない。
表現者塾に入っただけでは何も変らない。自分で自律して本を読んで一人で深めていかないとどうしようもない。
近代哲学派の考え
近代哲学といえば竹田青嗣、西研、苫野らであろう。
彼らは近代の設計をヘーゲルにみて、真理自身の自己差異の内省を介した弁証法的運動によって、人間の価値領域(本質領域)について動的に普遍性を構築する、それこそが近代の真の設計理念だと考える。
そのため問題は近代がそのような批判・内省をもたない硬直的自己同一性のシステムだと誤解され、反近代派の哲学者たちのその誤解が蔓延していることにあるとみる。
近代に対してその設計主語としてヘーゲルやルソーを立てる見方をする限り、この解釈は極めて強力で否定する隙が少ないだろう。
とりわけヘーゲルに対する評価はポストモダニストらと対極にある。
ところでヘーゲルは人間は動物と違い、対象と自己との関係(意味・存在・イメージ)を対象化し、さらにそのように対象化する自己自身をも対象化する自己意識を持ち、この自己関係の対象化の意識において、人間は自己価値の承認を言語=他者の承認に求める特異な存在であるという。
※動物の言語モドキは対象を示す標識でしかなく対象との関係を示すことができない。つまり人間の言語では対象と意味・イメージ・関係との差異が構成されるが、これが近代に至るとイメージと対象とをよりラジカルに峻別、つまり所与にあって対象の側にあったイメージ・主体性・霊性を主語・人間の側が所有し想起するものとして対象から完全分離する。このイメージの対象性の否定を介した近代における対象と意味との分離、主客の分離、の系譜的歴史展開に内在する第三象限・蓄積の暴力的作動(硬直的自己同一性の暴力)がキリスト教の自己放棄の自己技術を核としてフーコーでは問題構成され、逆にヘーゲルでは、この近代的分離の歴史必然的な心的傾向として、非分離と分離の非分離とでもいうような仕方で分離の暴力性が分離自身の歴史的展開において解消されると見なされる、このように理解するとフーコーの議論も現象学の議論もヘーゲルもその概要を今日的意義において簡単につかめる
※フーコーはキリスト教に批判的眼差しがあり、ヘーゲルはキリスト教賛美的、フロイトはユダヤ賛美的、一神教に対する評価も近代の評価と連動する
ヘーゲルのこの人間欲望の本質的洞察は僕の理解ではラカンの鏡像論や他者の欲望論の根底にも引き継がれている。ラカンはコジェーブのヘーゲル講義を受けていたようだからその影響かもしれないが、この人間欲望の本質論は深層心理学の基礎をなす。
さて、ヘーゲルはホッブスと同じく人間は承認を求めて闘争するが、敗者もどこまでも自由を求めるので普遍闘争と絶対隷属が止まらないという。そこで近代にいたり、自由の相互承認へと人間精神が到達し、この相互承認がラカンの父の名に対応するのだが、これによって万人の自由と平等の矛盾的同一(同一と差異の同一)の終わりなきヘーゲル弁証法が駆動する。かかる平等と自由との弁証法の運動が一般福祉を要請し、過剰な自由競争を抑制すると考える。
※禁止や抑圧を構成する近代のプラクシスな自由のあり方を問題視するのが一部のポストモダニストで、このために國分功一郎はスピノザに近代の抑圧モデルと異なるオルタナティブな自由(主体化)を探っているのだと思う、またポストモダニストではないフーコーも抑圧/解放モデルの近代主語制の自由と異なる自己差異の自由プラチックを古代ギリシャの自己への配慮・パレーシアに探った。フーコーは実際行為・述語・プラチックそれ自体の自由を近代自由の克服として提出したわけだ。さらに近代哲学派は自由における抑圧解放論が自由の誤認だということを現象学的に指摘し、この点で僕と近いが、この自由を巡る各派閥の認識の微差をおさえると哲学的な相互の位置関係を正確につかめるだろう、哲学理解のクライテリオンになるということ
※おそらく國分功一郎はフーコー好きなのだが、フーコー好きの僕とはかなり考え方も感覚も違う
このときルソーの一般意志は自由の相互承認を求める意志であり、ヘーゲルでいう一般福祉を実現する根拠ともなるだろう。
ここで現象学の重要な役割は、事をおかしくする近代主語制による誤認を、その主語主体性(認識主体・意識・コギト)において可能となった現象学的本質観取によって暴露し、誤認の問題を克服する点にあると思う。
またフッサール現象学の提出する動的真理モデルはヘーゲル弁証法に対応するもので、それゆえ現象学派はヘーゲル的な意味での歴史の完成(始まり)ととれる。
※現象学では客観的真理は、内的な確信において構成されると考え、主観から独立した客観像は存在しないと考える。つまりカントの物自体を消し去るニーチェ的な本体論の解体を引き継ぐ、この本体論の解体によって真理=普遍は信憑・確信の水準として訂正可能なものとして動的に一致可能となる、これにより真理はない!と叫び、普遍性を解体する相対主義を駆逐するのが現象学派の狙い、西部保守派が最大の敵としながらできなかった相対主義の打倒を達成してることに注意
なお西部はルソーやフランス革命を問題視するなかで、ロックとルソーとの違いとアメリカとフランスの違いを見失っている。
ルソーは一般意志において万人の自由のあるべき形態は、つど現在性において解釈され、その一般意志の解釈に基づいて過剰な競争を抑制するように、柔軟に法・制度がそのつど構築されると考えるが、これに対してアメリカを規定するジョンロックは、人権天賦説によって個人所有もろもろを神によってアプリオリに与えられていると自由プラクシスを独断論的に考える。
このロックの神による独断論的自由論が、個人所有の権利を神聖不可侵とすることで、アメリカの格差化による国家崩壊を招くに至る。こういうことを考えるのが近代哲学派。
※反米系の某古典主義者や某保守派が神がいたからよかったと熱狂していたがロックの神にもとづく人権論(独断論)がアメリカの暴走の原因だということがずっぽぬけている、このレベルがいまの保守で都合のいい話ばかりして情弱を欺そうとする
※保守派は異常に歴史好きが多いっぽいので歴史論を示すと、アメリカの愛国派=サンズオブリバティの建国精神の起源はインディアン(抑圧された身体性・無意識)のイロコイ連邦にある、しかしピューリタンは国土=身体を開拓して一方的に支配・所有する身体所有意識を拗らせ、ジョージワシントンは合衆国のアイデンティティにおいて、インディアンの大量虐殺を実行した、ここで国土身体(他者・無意識)からの声を抑圧したアメリカの歪んだ自由精神はそのまま個人所有=ジョンロックの身体所有意識を暴走させ今日の凋落を招いたように思う
そういうわけで近代派は誤認をつど自覚し引き受ける新しい近代主体をその哲学の中心軸とする。そのため近代主体性そのものをレジームチェンジするポストモダニストとは犬猿の仲だろう。どう考えても相性が悪い。
まして現象学的志向性の否定などは近代派にあるまじき。
このような全体的ポジションの異同を自覚しているのがポストモダニストと近代哲学派で、保守派だけが、そもそもこういう相互の位置関係をあまり理解しないまま雑に批判をしている印象がある。
話を戻そう。
近代哲学の考え
①主語主体が差異の動的同一を根拠に成立することの洞察
②普遍的規範の動的(訂正可能)な構築こそ近代
③誤認をつど克服する近代主体を超えた近代主体の嫡子として現象学的主体を新たな定型とした社会の実現
近代哲学派は僕の見立てだと現実的な哲学を主張していて、一般意志とその最善表現としての法の考えや一般福祉の考えは完成度が高い。対するポストモダニストの主体のレジームチェンジという野心はマッドサイエンティスティックな印象がなくもない。ともあれ近代派は現象学を近代型全体主義を克服する自己技術に設定しており、フーコーとはやや異なる近代自身の近代の自己超克を描く。
わかりやすくいえば近代主体の正統進化としての現象学的主体による近代自身による近代の乗り越えが、近代哲学派=現象学派で、ポストモダニストは非定型発達的主体という新人類をベースとした近代主体の外在的な打倒を目指す。
というわけで近代哲学派は歴史を近代主体的な同一性においてとらえがちなヘーゲルの視点で捉える傾向がある。近代主体の正嫡的な系譜を重視するために、哲学の歴史観がポストモダニストや保守派とかなりズレる。
※具体的には竹田哲学では、デカルトで物語的な独断論が克服され内在の不可疑性が確立、それを引き継いだカントで相関主義が成立し、さらにヘーゲルでカントの統覚の定型発達的な発展の系譜が捉えられ、ニーチェで本体論が始末されつつ欲望・権力への意志相関性が提起され、フッサールで二元論が現象学的な弁証法により克服されて、プロタゴラスやゴルギアス以来の課題であった相対主義が克服された、というような正嫡的・近代主体自己同一的な哲学の発展史が描かれる、まさに近代哲学の正統的歴史観
ただし、歴史の究極目的みたいなヘーゲルにありがちなおかしな見方は一切しない。そういうショボいレベルではない。あくまで旧来の近代主体的ではなく現象学的自己同一性が近代派の強みだ。
ただ近代哲学派も万全ではなく、近代の社会制度や空間構成、近代主語主体の構成が不可避に生じる誤認の作動といった構造水準の問題の分析を欠いている。つまり近代哲学に対する無意識の分析=ディスクール的プラチック分析の視点が抜け落ちているため、見えなくなっている水準がある。主語を排除して論理構造の水準に内在する大他者(構造)の欲望を洞察する哲学の読みが抜け落ちているといってもよい。ラカンを軽視しフーコーをなまじポストモダニストの仲間として処分してしまったために、近代哲学派が見逃しているものもあると思う。
※フーコーは現象学が衰退したのは言語に対して無力だったからだという。現象学的言語論は優れているが構造主義的な洞察も欲しい
かなりダイジェストで良くも悪くも僕の独自色が出た解説になったが、これが基本だと思う。この近代を巡るパースペクティブの違いを軸にすると哲学諸派の哲学書を生きたテキストとしてスムーズに読むことが出来るだろう。逆にここが分からないと哲学が化石になってしまう。
最後に近代哲学派の肝となる現象学について補足すると、現象学では自然主義的な認識、つまり自明視された経験的認識と時間認識の根拠を自己意識に還元し、経験的認識や時間のアプリオリな条件を抽出する。この認識におけるアプリオリな条件の洞察が超越論的(認識の認識ゆえ自己超越的ということ)と言われる。したがって現象学におけるエポケーの要点は客観⇒意識的認識/主観という因果関係を向き変え、意識認識⇒客観とし純粋意識の内に普遍客観認識の確信条件を探ることにある。この視線変更によって主客分離における両者の一致の不可能というポストモダンの相対主義レトリックを克服する。
かかる現象学が要請する真理の動的モデルはフーコー的読解ないしはラカン的読解においては、必然、浜崎の師弟関係論に決定的な仕方で関わるがそれは後の項目で述べる。
近代の現象学とポストモダンの要約
解説が分かりにくくなったので、ワンポイントを取り出し、そこだけコンパクトに示し、近代派とポストモダニストの違いを表現したい。
初期デリダなどのポストモダニストはカントの物自体=語りえぬものを取り出して、普遍的な真理などないという。これによって普遍性、普遍規範を解体する。
これを帰謬論というが、この考えを徹底すると、たとえば自由意志についても、私の意志を遡ると意志そのものが自生しているとしか考えられない事態となり、
よって自由意志はないといえてしまう。
※何かを自分の意志で思い浮かべたとしても、その何かを思い浮かべようという意志はそれ自体として生じたに過ぎないということ、もし思い浮かべようと意志したことを自分で意志していたとしても、今度はその意志がそれ自体で生じていると分かる、どこまで意志の原因となる意志を遡っても初発の意志はそれ自体として私の意志を超えて私の意識に自生・闖入していることになるから自由意志はないといえてしまう、しかしそれでも僕たちは日常、自由(能動)と不自由(受動)とを区別している、つまり本当の自由の条件は別にあって、ここに誤認があり、この自由をめぐる主語制の誤認が一般的意味と道具的意味との誤認をも構成する
ここでは認識における誤認が無視されている。つまりレトリックに過ぎない。
たとえば普遍的な真理は実際にはある。ただしそれは可疑性(信憑)においてしかない、というのが正しい。
この現実は夢かもしれないという相対主義はこうして懐疑主義によってなんでも、あんたの感想、に還元するが、実際には僕らは現実と夢を区別している。
つまり客観を構成・認識する条件は別にあるということ。客観は主観(内在)において特定の条件を満たしたときに可疑性をもって信憑・確信されてある。
すると近代主体に特徴される自由意志の主体の考えも変ることになる。僕たちは確かに突き詰めれば、自己主体=主語は自分の意志を自分で支配などしていないと分かるが、それでも僕たちは普段、自由意志がある状態とそうでない状態とを区別してる。
だから実際の自由意志の体験の内実と自由意志の一般的な定義とではズレがあり、定義は誤認・幻想に過ぎない。
※後の項で示すが、フーコーの権力論も近代主語的な抑圧からの解放という自由に関する想像的誤認を問題構成し、解放ではない自己差異の自由プラチックを提出しており、つまり近代における誤認を処理しようとている、ゆえにポストモダンとフーコーは異なる
このとき、自由意志とは本当は~な条件を満たしたときに信憑されるものだという自由の体感条件を現象学は取り出す。
対するポストモダニストは主体はない、近代主体=主語は嘘だ!とやかましい。しかし、近代派はそうではなく、誤認・差異がある、という。自由意志は自己が絶対的に行為や意志の原因として先行・支配している状態をさすのでなく、実際には行為や意志の他性(非自己性)を自己の意志として引き受けることで生じる、だから自由意志は存在する。
誤認があることを排除してしまうと、つまり実際の体験と後の認識とのズレを排除して完全な一致以外は認めない!と言い張るとポストモダン(ポスト形而上学者)になる。
※本体との一致の照合から真偽判断を発動して偽を連呼するコプラ依存のポストモダンは全体主義を逆生産する学問教義(ディシプリン)にある
以上が僕が考える現象学派とポストモダニストの一番分かりやすくて単純な違いとなる。
またハイデガーは近代主体を人間として標準化したわけだが、これが自由意志をあると定めることへのポストモダニストからの現象学者への批判となるのだろう。
つまり現実に非定型発達という現象学的な本質観取が成立しない水準の脱主体だらけになったのが現代社会で、そこで定型発達的な幻想=自由意志の主体を主張するのは無効だ!というニュアンスだ。
これは鋭い一撃かもしれない。現象学派は心理学的には弁証法的に安定化された定型発達主義という含みをもっているふしがなくもない。
この問題提起は表現者の哲学や主張とも直接的に関わるので保守はよく理解して考える必要がある。
僕がこのブログで展開する持論は、もし非定型発達を中心に社会を考えると、近代民主主義は近代主体以上の水準の主体を前提とする制度なので、社会が自壊するということ。
つまり非定型発達を標準化した世界がどうして持続可能性をもって文化的で文明的な暮らしを実現するのか、この論理の不在がポストモダニストの最大の欠点となる。
松本卓也の優れた芸術論を読んでも感じるが、表面のアートとやらでどうして共同体が可能だと考えるのか意味が分からない。他者を構成しないことの意味は分かってるはずで、そうしたら絶対にそんな世界がありえないことは分かるだろう。
この問題を克服しうる解答をしているのは山本哲士と現象学派(竹田青嗣グループ)いがいに僕は知らない。
表現者の保守派の場合はクライテリオンといって定型規範の復古を主張する気配を感じるが、その定型規範の構造上のバグ(近代構造の誤認の問題)が現在の惨状を生じているわけで、だから、単純にクライテリオンを取り戻すというだけでは足りない。
これが保守派の問題点。
また現象学の問題をいえば、現象学が近代主体において可能となる主語=主体=意識への還元をやりがちなために、語る主体を抜き取った言説の動態構造という視点が弱い気がする。他者=無意識分析(言語)とか構造分析がどうしても現象学は弱い印象をうける。
すると言語構造と社会諸制度との連動などが見えなくなってしまうのではなかろうか。つまり現象学がその歴史においてなぜ激しく誤解され非難されたかとか、今の日本のサービスの暴力、目の前の人間を無視してデータや肩書きで判断する思考停止猿の瀰漫といった問題に十分に応えていない気がする。
なんというか内在的に応えることを避けて、外在的に、近代の外部に近代の問題点の原因を見出している印象をうける。
なぜと問うこと、それが僕たちが言語の世界に誕生することの根拠となるわけだが、この問いを問いすすめてゆくための原理論を提出できなければならない。これこそが生の営みとして、言説に対する内省を構成するための条件であり、この条件を満たすことが過剰な権力関係の抑制を実現しつつ自己が自己からつど自由となる自由プラチックを実現する。
だから、社会や世界への問いとは既存の知の編制に従属することで自らその知を構成する自由を実現するものとなる。
後述するが現象学派、竹田青嗣の優れているのは、動的真理生産の提出と公共のテーブル=哲学のテーブルのアイディアにあると思う。保守派の師弟論と比べると哲学として自他関係論の完成度が高いのが分かる。
つまり保守派は近代全体主義を克己する自他関係論=師弟関係論=権力関係論を提出する責務があるが、自他関係の言語論を欠くためにそれが出来ていない。
竹田哲学とフーコーのパレーシア
さて、この項目では近代の嫡子であるカントに反近代を読解したフーコーと同じ読みを近代の正統にある竹田哲学に対して試みよう。
竹田青嗣といえば近代哲学の歴史を一気にすすめたといって過言ではないと思うが、その近代の可能条件を提出する哲学が、反近代にあるフーコーの権力論、統治性、自己技術の観点からも興味深いので紹介する。
※哲学の歴史をすすめるというインダストリアル(発展・進歩的)歴史観はポストモダニストにはない。ポストモダニストはインダストリアルを否定しヴァナキュラーな水準を称揚しがちだがこの二項対立こそインダストリアルに属す、コンビビアルが大事なのだ
また項の最後に参考にパレーシアを僕なりに解説してみる。
この議論は表現者の浜崎氏が固執する師弟関係=自他関係や学校教育論を考えるうえで絶対的に避けられないと思う。
竹田哲学では公共のテーブル、哲学のテーブルという概念が提出されこれが強調される。公共のテーブルとは共同体が存続する上で合意形成を試される価値観などについて、人々が自由に参加し現象学に即して論じ、その問いを深めるという仕方でもって解決へ向けた合意をつど形成してゆく動的真理の終わりなき弁証法的運動を実現する真理生産モデル。
したがって、ここには近代がフロイディックに構造化してきた、知と真理をめぐる自他関係の転換が実現されている。これは近代がそのパノプティコン的(否定神学的)な真理をめぐる言語の構造のうちに、その近代構造をぶち抜く、意とプラチックを内在することを示すだろう。
さて、フーコーの権力論ではディシプリン権力とパストラール権力があり、これらは監禁する政治、救済の政治に対応し、これに人口に統計的にアプローチする全体化の政治を加えたものを生権力と呼ぶ。
※権力関係論は個人目線から権力のプラチック、網の目の権力を捉えたもので、対する統治は主語的な上から下への統制の作動をプラチック(述語的)な観点から、統治の統治という仕方で捉えたもの、権力と統治性を重ね合わせて分析し自己統治(エートス)と国家統治(ポリティック)の連動を古代ギリシャにみてそこから権力関係から自由な自己関係として真理(アレーテイア)と自己とのパレーシア的な自己技術に自由な自己統治を見出すフーコー三角形が後期フーコー
公共のテーブルは、とりわけパストラール権力を根源的に規定する自他関係=権力関係に関わる。僕たちの世界はまず真理をおいて、その真理において法案を提出したり、社会の舵取りをしたりするし、諸個人においても、自分が何者なのか?という真理を決定することで人生の選択やつどの振る舞い、道徳という自己統治を実現する。
たとえば合理主義的な知の編制において合理的真理を絶対化すれば、その社会は合理的価値規範にもとづく真理生産のディスクールのうちにその真理に叶う制度設計をなし、その社会の構成員もまた自己を合理的知において確定しその真理のうちに自己統治を貫徹するということ。
したがっていかなる社会・集団も真理の政治=統治をもっている。
このとき、この真理をめぐって言語的存在たる人間の自他関係が規定されると分かる、あるいは根源的自他関係の諸形式に真理の形式が連動する。かかる真理をめぐる自他関係が他者への従属化のあり方を決定する従属化=言語化=主体化という権力と主体のあり方を決定するわけだ。
フーコーの話の一部を強引に簡略化するとこんな感じと思う。
※近代言語とは第三者にも関係=道具的意味(表現)が伝達されるもので、それゆえ言語的意味・一般的意味へと自己主体を組み入れる主体化(自己の言語による意味付け)のプロセスは社会的=公的存在へと自ら主体を言語的法に従属化=主体化することを意味する
※パストラール権力と諸個人の自己実現や経済との密接な関わりは漫画のカイジに分かりやすい、当ブログでもカイジをパストラール権力から解説したものがある
保守派の興味に照らせば、ここでの議論は師弟関係論に他ならず、師弟関係=家社会=母子関係であって家族論にも直結する重要な話。
さて、パストラール権力とは厳密にはキリスト教の司牧権力のことで、内面の全てを大他者(羊飼い)に告白しつくし、羊飼いがそれを意味付けて真理を生産し、羊(信者)を救済するモデル。このとき羊飼いは信者の羊を一人一人個人として扱い献身的に世話をやく義務がある(個人化する権力)。群れに対して、個々人に対応し個人化するということ。学校の先生は、まさにパストラールの典型であり学校とは近代の産物に他ならない。
※プラトンでは相互的対話だった自他関係が帝政期にロゴスを聞くこととと自己を熟視・傾聴することとに分離、さらにキリスト教により自己検証に肉欲の罪の観念と自己放棄が登場し、これを経ていまの学校教育がある、通信簿に生徒の人間性が決めつけられるが、教師による羊の意味付けが学歴を決定し、その羊の一生をコントロールする。このパストラールシステムによりケツ舐めマシンだけをピュアセレクトしてエリート化するのが日本の学校化社会の一面
フーコーは近代国家をパストラール権力の新境地と見なす。学校でもサラリーマンの上司と部下でもその関係性のモデルは近代社会の前身たるキリスト教にあるということ。
この個人化する権力の問題は既に述べたが、西部風にいえば、人生の意味や価値という真理の全てを経済的かつ科学的な定量的価値・意味に還元しつくしてしまう告白の搾取をベースとする自他関係にある。
さて、プレモダン世界では、酋長やシャーマンが大他者となり、共同体のつどの経験を神話的真理へと解釈してゆく。構成員が病気となればシャーマンのもとで儀式治療がなされ、病気が意味づけられてゆく。自他未分の世界にあるといってよく、それゆえ、神話というイメージ(精神)の世界と客観的な出来事(身体的病)とが区別されない。日本で言えば史実の歴史と物語がまざった古事記はその典型だろう。
※神話と史実の差異を心理学的差異といい、この差異がハイデガーの存在論的差異と連動する
この述語制の自他非分離が、近代社会構造にあたる主語的なパノプティコン的構造によって主語的未分離と化すとナチズム、全体主義やポスト全体主義に陥る。
※日本の空気全体主義では術語の主体化が生じる
※否定神学構造とは世界全ての意味に単一の起源を幻想すること、全ての根源足る単一の欠如を幻想し、それゆえその究極の欠如した根拠にその不在を埋める究極の意味を妄想するが、この妄想がナチス的な全体主義的真理を構成するに至る、またこの究極の根拠の不在に人間が重ねられることで科学万能論=ホモデウスが構成される、これは主語、自由意志、近代主体の誕生の負の効果でもある
※自由意志が悪いのではない、誤認が問題となる
さて、旧来のパノプティコン的な権力、自他関係では真理を知っていると想定された偉い肩書きの人=大他者がいて、庶民はその大他者に内面や症状を打ち明け、告白し、その庶民の直観なり違和感なりを大他者の知にそって言語化=意味付けし、真理を生産していた。
浜崎氏の師弟論も動画を観る限りこの構成をとっている。よき師とは弟子の言語化されていない直観を的確に言語化するものだ!と浜崎はいう。
もちろん、このような自他関係は近代化された社会空間では、全体主義に帰結する側面が強く、そのため宝塚イジメ問題や旧ジャニーズ問題などが大量発生してメチャクチャになる可能性がある。
そこで近代が全体主義化せずに安定した真理の体制(真理と権力関係との循環)を実現するとしたら、それはいかにしてか?
実のところこの可能条件こそが、竹田青嗣が提唱する公のテーブルなのだ。
ここで竹田青嗣は真理を巡る自他関係をなすパストラール権力が現象学という自己技術=自己関係において、どのように止揚されるかを示している。
公共のテーブルでは大他者が現実の人間に実体化することなく、つまり具体的な個人に神が投影・転移されることなく、それ(普遍性の根拠)は象徴的なものとされる。つまり全体主義では真理の主体として、究極の真理を知ってると想定された主体がヒトラーなどの現実の人間に投影・転移されて象徴的なものと想像的なものが混同・誤認される心理学的差異の混淆が問題となるのだが、竹田モデルの公共のテーブルではそれがない。
※ヒトラーでは血の象徴学と性の科学の二重性があるとフーコーは指摘するが、僕の理論だと、これは物語=イメージの水準が客体化・科学化する仕方で心理学的差異=存在論的差異が混淆している、想像的誤認を巡るこの混淆・差異の排除が全体主義の構造条件となる
※デリダは神を殺せなかったが、現象学ではある意味で神が処分されている
※この誤認をラカンは去勢の想像的誤認と呼びこれによって性別の規範化を論じる
カントでいう物自体を解体し、ニーチェ的に本体論を始末した現象学的真理モデルが要請する自他関係においては、全体主義的な誤認を形成する近代的自他関係が解体される水準があることを示唆するだろう。父としての神=フロイトが、その構造の内に動的に始末されたといってもよいかもしれない。
竹田哲学はフーコーとは対蹠的に主体の認識論から入って、近代の暴力的な自他関係=権力関係を解体し、真理の自己差異を賦活する自己技術を要請する公共のテーブルを近代の可能条件として提出していると見なせる。
つまるところ時局的にいえば父なき時代に父なしで安定した真理ゲームを始める、それが公共のテーブルの現在的意義だと思う。公共のテーブルでは保守派でいうような上から解釈・言語化してくる師父は登場しない。
最近の物語はカリギュラ2や新幹線大爆破(ネトフリ版)にも典型的だが、大きな物語も父(師父)も定型もない。この状態からクライテリオンを構築するのが公共のテーブルで、公共のテーブルでは精神分析における転移が否定されてしまっている。だからこの社会が実現したときには精神分析派の臨床実践が根本的に変更される可能性が高い。
余談だが、他の記事で書いてることだが、現代の変質したパストラール権力は非常に危険で、ネットのQ&Aサイトはその典型をなす。ここでは諸個人の違和感や直観、社会への疑問といった知の編制に関する根源的な欠如としての問いをかき集め、アーカイブ化、その問いを隙間無く塞ぐもっともらしいだけの合理的回答を即レスしてゆく。
あらゆる真理への問いは、高速で埋め立てられ、ここでは誰も自ら主体的に問うことができなくなる。というより問いと回答が分離されてしまい、問いを問う内省の次元が塞がれてしまう。
この自他関係がポスト全体主義を構成する、あたらしい全体主義をなす、というのが僕の考え。この機械仕掛けのパストラール権力関係に密接に対応して医療権力の肥大と医学コード化された身体幻想の蔓延が生じると僕は考えているが、これについては気が向いたら、伊藤計画のハーモニーという小説を軸に記事にするかもしれない。
さて、フーコーはパストラール的な告白の搾取(内面の言語化)の問題に対して、古代ギリシャの自己への配慮とパレーシアに活路を見出した。
パレーシアとは命がけでもって、既存の自己や他者への批判を伴い、信念に基づいて率直に真理を語ること。デカルト以降の信念と真理との関係は内的意識の明証に還元されるわけだが、古代ギリシャではパレーシアステートという真理を語る者の道徳的資質に委ねられる。
ここではエノンシアシオン=語る行為が真理を真実と一致させる。僕の甘い理解では真理とは一般的意味のことで、真実は実際に起きた事を示す。たとえば隕石が落下して日本が焼けたとき、隕石の落下は真実で、これを日本国の危機として意味づける(物語化)のが真理といえると思う。
なにか事象を語るとき、信念と確信をもって語る行為がその言表を真実であり真理とする。このような真理の主張をフーコーは自由プラチックとして重視した。
真実が話者に自身を語らせるところの衝迫・衝動としての信念が重視されたのだと思う。
僕の理解によると、現代では真理は一般的な意味であるから、主体=関係=行為が排除されて意味が客体化されている。そのため語る行為=関係は無視される。
だから口頭行為を真理の条件とするパレーシアとは、自他の非分離にある。またここでの真理は外在的なもので、いわば日常的意味世界の外部にある真実が語られるということを示すと思う。
※パレーシアでは真理=真実、両者に差異がない
ディシプリン権力(一般的意味・ルールへの調教)の問題は、真実(S1)を排除して真理(S2)を絶対化する態度なわけだから、つまり信号機を守れば絶対安全だ!と真実(実際の交通事故)を無視して思考停止にルールに盲従することが問題であって、ここで行為は真理の外部の真実を率先して真理化するさいの根拠となるように思う。あるいは真実が語るというべきか。
いずれにせよ、行為として信念が重視されるのはハイデガーが一般的意味の起源を道具的意味へと還元したことに近いのかもしれない。現象学も一切の普遍性を客体ではなく内的信憑=確信、信じることに還元する営みである。
※この真理における真実の排除がラカンの大学のディスクールに対応すると思う、ラカンやフーコーなしで、信号機の不思議な誤認の問題に応えるのは難しいと思う
くどい説明に感じられたかもしれないが、フーコーの狙いを理論化していかないと、たんに扇情的に自分勝手な信念をヒステリックに叫ぶのがパレーシアということになりかねない。だからここは妥協できない。
というわけで僕の未熟な推理によると、一般的意味=真理の主客分離(客体化)の解体がパレーシアの一つの狙いで、これがフーコー哲学の基底をなすプラチック分析=行為分析=術語分析という文脈で成されている。
このためにパレーシアにおいてディシプリン/パストラールの従属化の問題が解消されうると考えているのではないかと思う。
だから現代ではパレーシアステート(父)を探して依存するのでなく、自らがパレーシアステートになることが求められるはず。
ある種、ダイモーン的な感性、すなわち存在(あること)の他者性(非自己性)に開かれる存在体勢を構成することに自由プラチックの重きが置かれた、というのがパレーシアによる自己技術をなす晩年のフーコー三角形(真理ー主体ー【権力】)の意味なのかもしれない。
以上から分かるように、近代主体の可能条件をつきつめた現象学における真理モデルと分離技術=近代を徹底的に批判的に検証したフーコーのパレーシアとは、微妙な異同をみせているように思う。
補足するとパレーシアでは真理を語る主体と語られた言葉の文法上の主体と真理を語る行為(信念)(パレーシア的エノンシアシオン)との微差が重要となる。デカルトであれが文法上の主体はコギトであり語る主体(思う主体)との差異を同致され、客体化された真理は語り手の主観=行為から分離されて内容が吟味される。つまり想念と外界との一致であり真偽が問われる。
※語る主体と文法上の主体の同一が近代の特徴、この同一が内面を構成して外界と内面を分離するが、この分離がキリスト教の自己放棄と罪の自己技術を経て可能となる、ということだと思う
※コンシアンスも古代ギリシャでは意識や良心ではなく振る舞いというニュアンスであり、キリスト教による内面の誕生、心身二元論によってコンシアンスは良心や意識=内面と見なされるようになったのだと思う
対するパレーシアでは非分離のためにプラチック=行為=信念(パレーシア的エノンシアシオン)が重視される。
余談だがフーコーのパレーシアで重要なのは、語る行為それ自体の水準が基準となっている点だ。目的意識における対象の側ではなく、行為それ自体の自律性=自由が重視されており、それゆえに自由だということ。
西部ワードでいえば、蓄積や表現によって暴力的に伝達が規定されつくすのではなく、伝達=行為の側の自律性が逆に蓄積や表現を規定する水準があり、この水準を賦活するのが近代全体主義を超えるフーコーの自由プラチックだということ。自由プラチックとは主体の自由ではなく行為自身の自由なのだ。そしてこの自由プラチックにおける真理、事実、主体、他者との関係がパレーシアにおいて洞察されている、と僕は考えている。
中心的理論
記事が長すぎるので重要なロジックをタイトにまとめたい。この記事で中心にある理論を示す。
まず西部は自身の著書で全てを定量的な価値と意味に還元しつくす近代の経済至上主義を批判。
これがフーコーではキリスト教時代に変質した自己技術をなすパストラール権力における告白の問題として洞察される。
つまり自身の内面の全て、隠された真理をあますことなく告白し言語化して言語的意味に還元しつくすよう迫られ、そのことで意味・規範に自ら率先して従属化する主体の問題を扱った。
このような主体の自発的な従属化が空間・建築の構造では近代におけるパノプティコンに対応し、この自ら率先して自己を従属させる主体の自由のあり方がディシプリン権力やパストラール権力としても捉えられる。
※自発的な従属化が権力関係にあるとは、権力関係は自由によって可能だと言うこと
これがフロイトでいうトーテムとタブーにある原父殺し(超自我の内面化)に対応し、ラカンの男の式、ポストモダニストが警戒する否定神学構造に対応。
※告白の全てを言語化する作業はラカンの強迫神経症=男の疎外(S1→S2)のあり方と完全に同じ
またこのときディシプリン権力がなす身体への調教は、ラカンでいう享楽の局在化に対応。
※享楽の局在化は定型の性規範に対応し、これは宮崎駿の魔女の宅急便にとくに顕著、現代社会分析では、すずめの戸締まりと魔女宅を比較するのが大事、ディシプリン権力は身体=ファルスを持つことであり去勢に対応する、これにより主従形式=所有形式が規定され所有形式と時間の構造化が対応する
フーコーの系譜学では、ギリシャ的な自己への配慮の自己技術がキリスト教を経て従属化と自己放棄の自己技術に変質したことが探られる。
フーコーは主語制=近代国家の知の編制にある権力所有論を否定し、これと密接不可分のこととして、性の抑圧からの解放といった解放による自由の獲得という近代の自由/抑圧モデルを否定し異なる自由プラチックを古代ギリシャに見出し、統治制と権力の問題を克服しようとした。
このことはフーコーにおいても誤認が近代の問題として扱われている動かぬ証拠だと思う。
※フーコーが指摘する抑圧なき自由という近代的自由の誤認は、この記事における意味の存在論的差異の誤認と同じ、僕はずっと以前から自由の誤認と存在論的差異における誤認を対応させて考えてる
※フーコーは反国家ではなく国家の非国家化、国家の非実定化を示す
※自由をめぐる性の抑圧論がフーコーでは狂人/理性人(狂気の歴史)、犯罪者/普通人(監獄の誕生)、病人/健康(臨床医学の誕生)といった二項対立をなす規範化・制度化にも連動すると捉える
この自由の誤認の問題がキリスト教的な言語化の暴力をなす告白の自己技術=主客分離技術として問題構成されている。西部の近代への問題意識もここに通じている。
しかし現象学という近代主体の嫡出子は公共のテーブルにおいて、真理と権力との関係における告白の搾取モデルを破壊するに至る。
自他関係=権力関係における誤認をなす他者が想像界から消去されてしまったからだ。このことは現象学が本体論を解体して、主客の二項対立を粉砕したことに関わる。
近代の申し子、カントに非近代を読み解いたように近代に内在する非近代の自己技術が現象学のうちにあったと考えられる。
このような近代がもつ破滅的全体主義化(統治制の一般化)と現象学モデルによる主体のサステナブル化(批判)のふたつは、言語へと疎外された主体の生が抱える理想が現実になったときには心的外傷になってしまうという欲望のアンビバレントに起因するだろう。
※全体主義は主体の理想であるがゆえに同時に主体の死(心的外傷)であるから、近代が生の道を探ろうとするときには現象学の真理モデルにいたるということ
※現代では誰もが全体主義を少なくとも表面的には否定するし望まない、にも関わらず渇望されて全体主義化する作用もありアンビバレント
現象学の真理モデルでは、真理を知っていると想定された主体は想像界にはいない。だから表現者クライテリオンがいうような意味での師弟関係は無効化される可能性があり、精神分析の臨床実践からも転移が消滅する可能性がある。
人文学書の三つの読み方
さて、最近は人文学書の読み方すら分かってないとんでもないアホが、知識人ぶって人文学問系YouTuberとして跋扈し、金稼ぎのためのゴミ動画を乱造、結果、大衆の矮小な脳細胞は汚染され、さらなる脳萎縮の新境地へ至る新人類・ニューモンキーが後を絶たないと思う。
まったく研究能力のない、なんの実力も実証できない人文学系YouTuberが偉そうに本の読み方を説いていて呆れる。頭がおかしいとしかいえない。本当に専業YouTuberで人文学を学ぶのだけは辞めて欲しい。
だから、人文学書の読み方を簡単に示す。
まずイマドキの終ってる読み方はポストモダンに起因する。とくに作家の死は非常に害があると思う。これのせいで、自分勝手に支離滅裂なバラバラの解釈をしてゆき、分かるとこだけを拾って多読乱読し、信念補強的な妄想を強化するだけの迷惑系クイズバカが繁殖していると見える。
そもそもYouTuberでもやたら偉そうな参考文献を複数冊示す、頭のゆるい自称哲学系がいるが、そいつはまともにその参考文献を読めてない。YouTubeで参考文献を載せることがいかに無意味かよく分かる。普通の人が参考文献を当たっても専門書は理解できないから意味ないし、専門書を読む能力があるなら、参考文献などあたらなくても情報の質は判断できる。つまり自分の頭で判断できない情弱相手に参考書籍の権威でセルフブランディングするアホYouTuberだらけ。
※参考文献だらけの論文もよくあるが、理屈が全て書いてあれば本来、参考文献を載せる必要はない
※西田幾多郎の代表的な学術論文には参考文献などないものがあるし、柄谷行人にもほぼ参考文献なしの論文がある、参考文献主義はスネ夫的日本人の特徴
※参考文献や引用論文を記事の権威性とするGoogleは人文知を根本的に勘違いしている
またバカな院生がしつこく参考文献を聞いてきたことがあったが、言語学の院生が読めるような程度の本を僕が読むわけがないだろう。こういう研究能力のないやつは該当箇所だけ読んで分かったつもりにでもなるのだろう。どこまでも本をバカにしている。
さて、YouTuberはシリーズ動画を排除する、後編の動画は前編の動画を観た人しか観ないから、かならず前編より再生数が落ちる。そのためYouTuberは一話完結のカッスカスのカス動画を乱造するようにシステムに強迫・脅迫される。
ゆえに人文学問系インフルエンサーは学問知を商品として消費させるにあたって教養や賢さ=本の読み方の定義をいじくりまわすこととなった。
賢さや教養は、本来、知識の量ではなく自らの主観・主体として深く専門知を身につけ、その深い理解を手がかりにより理解を深めることで幅広く諸学問への見晴らしを持つことだが、現代では、手当たり次第に、あらゆる人文知のその表面だけを知識としてかき集め、それらの結論だけを箇条書きで効率的に暗記するクイズマンになった。速読・多読による書籍の大量消費を煽り、本の要約動画を早送りで大量視聴することが教養や賢さであると錯覚させる手口も多い。
こんな読書や動画視聴はやるだけバカになる、知の破壊でしかない。クイズ芸人と学問は関係が無い。
國分功一郎はこの趨勢にあって、哲学書は分かるとこだけ拾い読みすればいい!と棹さすわけだが、
このふざけた読みをしてはいけない、どんどん頭が悪くなる。どういう感性でこういう発言がでるのか理解できないが、こういう人が大学教育をしているから、人のブログ記事を分かるとこだけ部分的に読んで曲解してくるトンデモ院生が沸いてくるのだろう。
世間に迷惑な教育者としか言い様がない。
※國分功一郎は他にも自身の野望は、柄谷行人以外にも日本人の哲学を世界へ、だという。これはリップサービスなのだろうか?くだらない
さて、近年人文知は哲学を中心に急速に劣化している。優れた哲学の仕事が年配の哲学者によるところが多いのがその証拠だ。偉大な先人の書籍生産のおかげで、現代ほど簡単に学べる時代はない、にも関わらず若者の人文知の論理生産は劣化している。
※たとえば山本哲士以前に僕のような一般人が日本語でフーコーを理解・了解するのはほぼ不可能だったはずだが、山本の本のおかげで、僕でもフーコーを味わうことが可能になった。本来ならフーコーブームになるほどの変化である
僕には、現代人は主体が溶けてしまい人文学を成立させる知性が人類から消滅しかかってみえる。とりわけ英米系の分析哲学の劣悪ぶりにはうんざりさせられる。
おすすめの読み方
①近代主体的読み⇒現象学的主体の読解
これはその著者が何を問題と考え、葛藤しているのか、その著者の根源的問いがどこにあるかを行間に探ってゆく読み。
つまり本に論理が書かれているわけだけど、その論理を機械的に理解するのでなく、なぜこのように考えるのか?(動機)を徹底的に欲望してゆく読み。
このような読みの形式をラカンは欲望とは大他者の欲望を欲望すると言っている。
これは建築構造でいうとパノプティコンに相当する。テキスト(各監獄)を監視して意味づける不在(見えない)の著者(監視塔の中の人)の監獄への目線(欲望)を主体的に探るということ。単一の不在を探ってテキストの全体性をつかみ、体系的に理解しようということ。
普通の人間なら言われなくても、自動でこの読み方になるのだが、イマドキは人間がぶっ壊れているので、いちいちこういうことを言わないといけなくなった。だいたいここが分からないとそもそも納得できない。相手が何がしたいか分からない状態で相手の言ってることをリテラルに理解しても意味不明だと言うこと。
より厳密には、テキストの結節点となる著者の欲望はつど現在性においてある、という意識が重要で、これがないと独断論になりやすい。つまり厳密には現象学的(相関主義的)に読む必要がある。
②深層心理学的読み。これは深層心理学をやってる人が哲学の本を読むときに自動強制的に作動する読み方。僕は自動でこの読み方が最初に生じるようになっている。たとえばデカルトの懐疑主義/二元論/明証を、主客の分離における現実原則の生成において生じた哲学だ、と精神分析的に読んだり、心理学的誕生の効果だ、とユング派的に読解するスタイル。
※ラカン派や木村敏ではデカルトのコギトは悪霊に対する防衛としての中動態ー能動態的なものとして読解される
この読みはフーコーやヘーゲル弁証法の歴史哲学的な読みとも関連してくる。いずれにせよ、これを使うとある程度、通時的にも共時的にも読める。
またこれにプラスして著者の無意識を読むことをする。たとえば、カントの脳病試論や統覚の規定、人間学などの記述の年代的な狂気を巡る考察のブレから、人間理性と狂気に対する無意識的な葛藤の表れを読み解くなど。ここではカントのテキストの変遷の根拠が狂気をめぐるカントの無意識の葛藤に探られている。カントには狂気を人間の条件としたり逆に人間の条件から狂気を排除する記述のブレがある。
※カント哲学の無意識の読解は当ブログで松本卓也の芸術に関する本の解説をした記事で説明している
③フーコー的読解。フーコーは哲学を言説プラチックや自己技術、思考技術として読む。これは著者という主語を消去して、その言説の効果や言説に内在する意を洞察する。現象学がつかみ損ねがちなディスクール的プラチックを浮き彫りにするような読み。僕の理解では他者=無意識の主体の読解に通じる。
また知ー権力ー主体のフーコー三角形に対応する自己技術・思考技術として哲学を読解することでもある。
この記事で言うと、前述した竹田哲学の公共のテーブルに対する考察やフーコーのカント読解がフーコー的読解になる。
というわけで、本の読み方は自己同一性のあり方に対応する。
フーコーのエピステモロジーの観点で補足すると、当ブログで問題構成してきた論理言語学/主流派経済学/行動心理学のエピステーメー(見出されるところの諸経験科学の時代層ごとの全体性)の主語制論理の問題は、フーコー三角形の近代経験科学に属する、話すこと/働くこと/生きること、の三つに対応する。
これは人間存在を諸主体へと変容する客観化の三様式のうちの一つ、話す主体/生産主体/生の事実に対応する。
このようにフーコーを読む以前から僕の研究は、フーコーの考えと親和性が高い(興味が近い)のだが、この近代的な学問教義=ディシプリンの最終形態として、ポストモダン的な読書スタイル(知)の氾濫が生じている、というのが僕の読書論が提示する問題構成となる。
※具体的ロジックは当ブログの他記事で提示しているので割愛
ここで問題構成とは、リベラルアーツすなわち自由プラチックとしての思考技術=述語技術を示す。
つまり現代人の本の読み方がおかしいのは、そいつがバカだからだ、とか教育制度が悪い、という主語制(プラクシス)の問題構成それ自体を問い、つまりその問題設定を問題構成して、その主語的な問題設定の条件を洞察し、これにより既存の思考地盤をひっくり返そうというわけだ。
問題構成こそが最良の問題解決の反応を可能とするといってよい。フーコーの哲学はこの意味における問題構成と思考技術の哲学である。
※道徳プラクシスに対応する制度を問題構成すると制度と主体との権力関係論が排除されて制度改革という幼稚な処方箋しか提出できなくなる。ゆえにフーコーの権力関係論は制度論を超える問題構成であり問題/処方箋の分離技術を克己する原理である
※保守派では唯一、中野剛志が、この問題構成の決定的重要性に気づいているようだ
終わりに:ギブ&テイクの教育論の落とし穴
最近ずっと山本哲士の『ミシェル・フーコーの思考体系』を読んでいる。その影響でフーコーに関する記述が多めになったが、フーコーの魅力は計り知れない。
世間で売れているフーコーの解説書など山本のフーコー書と比べると、ほとんど無価値と思う。
近代の問題を研究したフーコーの理論はフーコーの問題意識を少なからず共有する保守派には欠かせないものと思われる。
さて、焦って書き殴ったためにまとまりを欠き長くなりすぎて誰も読まないだろう記事になってしまった。5万字を超えたため見直しがあまりに面倒で、かなりいい加減な記述が多かったと思う。まったくまとまっていない考えを書くと無意味に長くなってうまくいかないと分かった。
ともあれ、この程度は理解しようということでこの記事ができた。この複雑化した社会で全体の理論的見晴らしをつけようとするとどうしても小難しくなる。
保守派への素朴な感想を述べると西部と表現者クライテリオンに微妙ながらズレを感じる。山本七平をそのまま引用して語るだけで満足してはいけない。西部がいうように山本七平のロジックは物語的でそのままでは使えない。言語構造論に転移しないといけない。
さて、最近、浜崎氏のギブアンドテイクの教育論が元クライテリオンの執筆者との間で激しい論争になっていた。その恩を返せという浜崎式の教育論は、主語制の論理にあって関係に対して主語主体を先行する構成を感じなくもない。
※じつのところ、記事で表現者を扱うきっかけがこの論争
なんらかの行為がギブと呼ばれるためには、行為の主体として私という主語が立てられねばならないからだ。たとえば(これ)あげるといった場合あまり主語は意識されないが与えると言うと与える主体を意識させられる。与えるは他動詞で分離した他者(与えられる人)の視点を猛烈に意識させるのでなんだか受動態に通じる一神教的な感覚が僕にはある。
また、私がしてやったから恩を返せ、というのは関係源泉的行為を遡行して主語に還元し、その行為の向きを固定する操作と思う。おそらく浜崎氏の狙いはギブ&テイクは分離できない、だから循環的な因果関係をなす関係水準だ、という感じなのだろうが、いかんせん主語的なニュアンスが強いだろう。
おそらくこれは義理人情、恩を返すという日本文化を教育論、師弟関係=自他関係論に落とし込み日本人論の基礎とするための思考操作の結果だろう。
ありていにいえば、結論ありきで考察してるような印象を受ける。いくつか動画で論旨を確認したが、関係を先行させるニュアンスでギブ&テイク論を主張するのは苦しいと思う。
あと浜崎氏は柄谷行人が好きらしいからギブ&テイク論には、柄谷の交換様式Aの贈与と返礼があるのかもしれないが、すると浜崎論では浮動民Uがない。だから個人を関係に束縛する贈与の負の作用を強く感じる。
また、ギブというとギフテッドという流行言葉を想起する。僕はギフテッドという言葉がかなり嫌いなのだが、それは関係を切って才能を個人の主語主体に帰結させるからだ。まるで才能に本体があるかのようなプレモダン的でイマジネールな真理モデルを前提とする言葉だと思う。才能(知能指数?)は関係であって実体ではない。
これは主体化における知性/性格の客体化に他ならず、フーコー的にも見逃せない。このような自己をめぐる原始的真理の台頭は危険であり、この危険な思想もギブの思想と切り離せないように思う。自他を分離して与えられたと受動態で捉えるのは微妙なので、非分離・非自己(山本哲士)の水準で中動態的な契機を読み解く方がいいと思う。
以上から、師弟関係ー国家保守ー学校主義ー国語の系譜にあってギブ&テイク論が言われている疑義が濃い。
※受動態の成立が近代主語の成立に密接に関わる、与えるという語は取り扱いを間違えるとおかしなことになる
さて、僕の考えでは、義理人情というのは対象以前の関係項なき純粋な間における集団主体的な存在規制(気・空気)に関わる。この集団主体的存在規制から個人が分離するときに、済まないことをした、という事態が起きる。だから教育(個育て)というのは、恩義が裏切られる瞬間にその真価が問われる。
それは、もののあわれ、に通じるが恩義が裏切られて、これが美的解消へと至る様を古事記や日本の昔話は延々と繰り返している。見るなの禁を破ったイザナキや山幸彦はその典型だ。あるいは鶴女房やウグイスの里もその典型であろう。
だから昔話プラチックを読み解くこと、あるいは恩を裏切って排除されたものの側から、文化の正統を逆照射してゆくフーコー的・深層心理学的読解、つまり意識から排除されてある、語られなかったものとしての文化を見抜く必要がある。
恩を返せという教えを、恩を返すことと洞察するのは少し苦しいと思う。
そもそも浜崎教育論に反抗期はあるのだろうか?関係の切断に恐怖を植え付ける浜崎式は、まさに悪いことをしたら家に入れないという負の日式教育の再来ではなかろうか。欧米では悪いことをしたら外出禁止なんであって分離を欲望させる教育が徹底している。
アジア的なものは自己技術が最初からなく、他律技術が優位とされる。浜崎教育論もやや他律的な教育技術となるだろう。もっとも今の日本社会を生き抜くなら他律技術を適度に身につけた人のが有利だろうが。
※浜崎教育はプロテスタント的な厳しさと日本式の他律化の奇妙な二重性が強い印象を受けた
ともあれ、始原の根源的今に逗留することが望郷されつつその不可能性が悲しみ、もののあわれとして表象される、ここに日本人の自他関係の淵源があると思う。
ただでさえ義理人情でしつこい人間関係を要請する日本文化のその補償として、恩を裏切りったことの怨恨の美的解消の主題と、仏教の恬淡とした人間関係が重視されてきた、それが日本の伝統と思う。
少なくとも僕は人間関係をギブ&テイクとは考えない。いちいちこんな風に考えてる人がいたら恩着せがましいからだ。
ニーチェを好むフーコーであればギブ&テイクは出来事化(偶然の連続化)に過ぎないというだろう。僕もそう考える。
※最近増えてるストーカーがあんなにしてやったのにと、女性を刺殺する事件もギブ&テイクの発想
※カリギュラ2に押しのアイドルが裏で恋愛やっててキレて、決して裏切らず世話をやくと必ず応えてくれる植物に熱中するキャラが登場するが、これもギブ&テイクの病
※義理人情連呼の某ネオリベ系バカ保守がギブ&テイクの義理を裏切ったとネットリンチ・内ゲバをしまくるのが今の日本
浜崎氏の倫理はカントでいえば仮言命法になるが、浜崎倫理学によるとギバーは経済的にも成功するという。僕には成功するからギブしろと聞こえ、ここにも違和感がある。だったら僕はギブしない。
※成功者がギバーとなんで分かるのか、ギブに対して行動主義的な定量化をしている疑惑があり問題を感じる、明らかに俗耳に入りやすくそれゆえに危険性を感じなくもない
他者の見返りに依存し成功に依存する、仮言命法ゆえに他律思考に陥る。このブログも公共や読者にギブしているとは思ってない。ただ考えをまとめるので書いている。公に開示する都合で公的内容に調整してあるというだけで他に意味は無い。
僕が勝手に書いているだけ、だからこのブログは継続できている。
※仮言命法はおそらくフロイトの現実原則に対応し、現実原則の絶対的優位化が西部や僕が問題視する理想なき現実主義のことで、これがフーコーで言う従属化=主体化を生じる
仮言命法を否定したが、定言命法がいいというわけではない。そのつどの過去や蓄積の因果から断絶した判断があるというだけで、その非自己の断絶が自律だということ。それが仏教のとく諸法無我であり今であろう。
すると人と人との関係も、対話ならただ聴くというのが正しいと思う。何かを上から言語化するのではない。そのような言語的同一性の対象として対峙するのでなく、沈黙として、語り手の言表行為そのものとして対峙することが求められる。
※前述したように浜崎論によると理想の師は弟子の言語化されぬ直観を的確に言語化するのだという、これは初期フロイトの症状論にも近いが、このこととギブ&テイク論は関連するだろう。つまり問題と処方箋の分離がある。またラカンなら弟子が満足する言葉は決して与えない。それがフリュストラシオン/不満足、分析の命だからだ
ギブ&テイク=恩に報いろと言われているとき、そこには言われていないことがあって、その欠如を読む必要がある。
そもそも表現者はどうどうとクライテリオン・規範の定型を世間に提出してゆく。何か知を知っている主体(予言者、大他者)の位置につける感じで、みんなで議論して考えようという雰囲気が弱い印象をうける。フロイディックだといってもよい。フロイトの精神分析がニーチェの神殺しの宣言の後、あるいはフランス革命の後、処刑した父をその父の死において復刻すべく生じたバックラッシュ理論だという洞察は学問の世界では定番だが、
いわば表現者はクライテリオン(定型=父)の消失したポストモダンの今日において、フロイト的定型=近代主体を復古する定型主義の保守思想なのかもしれない。歴史における二度目の父の死にあってフロイトを再演しているように見える。それはくしくも今日のポストモダニストがデリダの現象学批判を別の水準で、現象学的指向性の排除として再演することとシンクロニシティにある。
いずれにせよ、表現者の哲学は、近代主体的=国家保守的に見える。国家の外部にある場所制=日本語を洞察してゆかないと日本文化論の組み立てはほとんど無理だろう。ゆえに西部の言語への転換を実現する場合、西部の国家実定化を否定することで西部思想を達成する以外に手段はないだろう。
というわけで浜崎氏の師弟論を動画で拝見したが、やはりロジックがやや雑な印象があり、全体主義の考察も聞いたが論理が甘くやや雑に感じた。
文芸評論家と僕のような探求者とでは知への態度が違うのかもしれない。僕は妥協せずエッジのギリギリ限界までいきたい。
一般論になるが広く日本の保守派といえば、義理人情とか師弟・家族関係をやるせいで、縁故で身内に仕事を回しすぎて実力の低いコネ野郎やケツ舐めばかりという印象が強い。哲学という観点でみた場合、他の派と比べて哲学の理論がやや雑なのは事実だと思うのだが。保守派は歴史や経済は博識で他に抜きん出ていると思うが、哲学論理は過剰な大衆化や身内びいきのせいか質が落ちる。
※表現者を、同じ京都大学で同じく村上春樹好きで村上文学の魅力を伝える論文を出したりしている河合俊雄のグループの現代社会分析と比べると、やはり哲学の質が一枚落ちる印象がある、ちなみに村上春樹とユング派は古くから交友がある
ところで、やはりフランス現代思想や日本思想を探るなら、山本哲士の哲学が圧倒的と思う。山本思想のレベルは他の追随を許さない次元にあり、ポストモダニストの実力者すら雑魚に見えるほど。
※僕の個人的感想だが、フーコーのことが好きそうな國分の哲学は読まずに言うのもなんだが、フーコーからやや後退して感じる、しかし山本は確実にフーコーのその先を走っていると思う
また近代哲学ならば竹田青嗣に限ると思う。竹田哲学はアンティークのお飾りと化した近代哲学を今日の実践に耐える域に高めたと感じる。
おかしなプライドを持つとどんどんおかしくなる。西部の残した日本語論の宿題をやるならおとなしく山本や竹田らの本を参照した方がいいし、松本卓也などのポストモダン系の良書を読み込んでしまった方がいい。歴史知識と経済知識の豊富さはもういいから哲学理論をもっと固めた方がいいと思う。
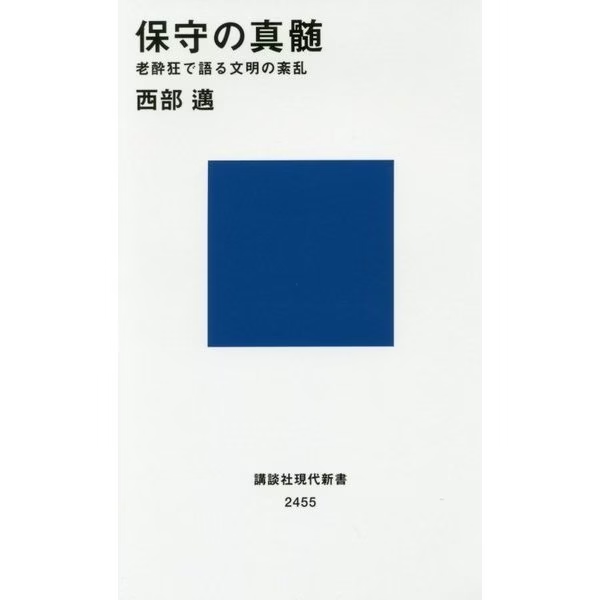
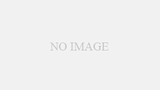
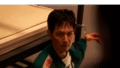
コメント